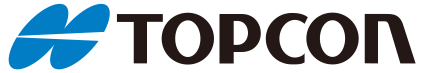- Start Date
- 2026/02/10
- End Date
- 2026/02/10
- Event Details
-
日程:
2025年12月23日(火)
2026年2月10日(火)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、福井コンピュータ株式会社
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-fukui-computer-2h.html
- Target
- _self
DX
デジタルツインとは?災害とインフラ老朽化に立ち向かう建設DXの最前線

建設業界で今、「デジタルツイン」が大きな注目を集めています。これは、現実世界の情報をリアルタイムで仮想空間に再現し、高度なシミュレーションや現場管理を可能にする技術です。
熟練技術者の不足、インフラの老朽化、そして激甚化する自然災害。こうした社会課題の解決策として、デジタルツインはどのように活用されているのでしょうか。
本記事では、国土交通省が進める国家プロジェクトから、実際の施工現場での活用事例、そしてインフラ整備や災害復旧における今後の展望まで、建設業の未来を左右するデジタルツインの最前線を解説します。
建設業界で注目されているデジタルツインとは

デジタルツインとは、ドローンやセンサーなどから取得した現実空間のさまざまな情報をもとに、まるで双子(ツイン)のようにそっくりな環境を仮想空間上に構築する技術です。
単に3Dモデルを作るだけでなく、現実世界の変化をリアルタイムに反映できるのが、デジタルツインの最大の特徴です。これにより、高精度な現状把握や未来予測のシミュレーションが可能になります。
2002年にアメリカで構想が発表されて以来、ICTやAI技術の進化に伴い、さまざまな分野で活用が期待されています。
【参考】総務省「デジタルツインって何?」
広がるデジタルツインの可能性
デジタルツインが活躍する舞台は、建設業界に限りません。交通分野での渋滞予測、都市計画における人流シミュレーション、製造業での生産ラインの管理など、さまざまな場面での活用が期待されています。
デジタルツインでは、現実空間では難しいテストや危険を伴う検証を、仮想空間上で何度でも安全に行えます。つまり、あらゆる分野で生産性や安全性の向上に貢献する技術であることが、注目の要因として挙げられます。
その市場規模は急速に拡大しており、2022年に99億ドルだったグローバル市場は、2035年には約63倍の6,255億ドルに成長するとの予測もあります。このことからも、デジタルツインが未来の社会に不可欠な技術であることがうかがえます。
【参考】総務省「令和6年版 情報通信白書」
「3Dモデル」や「BIM/CIM」との違い
デジタルツインと混同されやすい言葉に「3Dモデル」や「BIM/CIM」があります。それぞれの違いを理解することが、デジタルツインの本質を掴む鍵となります。
3Dモデル:物体の形状を三次元で表現した静的なデータです。作成した時点の情報で作られ、現実世界のリアルタイムな変化は反映されません。
BIM/CIM:3Dモデルに、部材の仕様やコスト、管理情報といった属性情報を加えたものです。主に計画・設計・施工・維持管理の各段階で情報を一元管理し、業務効率化を図る手法として活用されます。
BIM(Building Information Modeling)は建築分野で先に発展し、国土交通省はこの考え方を土木分野にも展開するため、2012年度からCIM(Construction Information Modeling/Management)の試行導入を開始しました。- デジタルツイン:BIM/CIMなどで作成した3Dモデルをベースに、さらにセンサーなどから得られるリアルタイムの動的データを連携させたものです。現実空間の変化を常に反映し続け、シミュレーション結果を現実世界へフィードバックできる双方向性を持ちます。
ただし2025年段階では、完全なリアルタイム連携は実現に至っていません。多くのケースでは「高頻度での更新」や「人による修正・補完」を行って、現実との整合性を保っています。
BIM/CIMが建物の設計図やカルテだとすれば、デジタルツインは「生きている双子そのもの」と言えるでしょう。
【参考】国土交通省「BIM/CIMの概要」
【参考】国土交通省「i-Constructionの取組について」
なぜ今、建設業界でデジタルツインが重要なのか

建設業界は、社会の安全と暮らしを支える重要な役割を担う一方、多くの課題に直面しています。デジタルツインが、これらの課題を解決する切り札として期待される理由を3つの側面から見ていきましょう。
激甚化する自然災害への対応(防災・減災)
日本は、自然災害が非常に多い国です。気候変動の影響による豪雨や台風の激甚化に加え、地震や津波、土砂災害など、常にさまざまな脅威に晒されています。こうした脅威から人々を守るため、インフラ整備や災害発生時の迅速な対応は不可欠です。
デジタルツインを活用すれば、都市やインフラの情報を仮想空間に再現し、災害のシミュレーションを行うことができます。
【事前対策】
・豪雨による河川の氾濫や内水氾濫の浸水域を予測
・地震発生時の建物倒壊や延焼範囲をシミュレーション
・津波の到達時間や浸水域を予測し、効果的な避難経路を策定
【発災時】
・ドローンなどから得た情報で被害状況をリアルタイムに把握
・孤立集落の発生や寸断された道路網を特定し、救助や復旧の優先順位を迅速に判断
これにより、災害に対する社会全体のレジリエンス(回復力)を飛躍的に高めることができます。
インフラ老朽化対策の必要性
インフラの老朽化も、デジタルツインに注目が集まる理由のひとつです。国土交通省の発表では、高度経済成長期に集中的に整備された橋やトンネル、下水道などの社会インフラは、今後、建設後50年以上が経過する施設の割合が加速度的に高まることが指摘されています。
同発表では、2030年には橋梁の約54%が建設後50年を超えることが明らかにされており、これは決して看過できない重要な課題です。
デジタルツインは、この老朽化対策を効率化・高度化します。
センサーなどでインフラの状態を常に監視し、変化を記録
人が近づきにくい場所も、ドローンなどを活用して安全かつ効率的に点検
損傷が深刻化する前に修繕計画を立て、インフラの長寿命化を実現
点検・管理コストを大幅に削減
計画的な維持管理によって既存インフラの安全性を確保できれば、将来的な建設コストの抑制にもつながるでしょう。
【参考】国土交通省「社会資本の老朽化の現状と将来」
生産性向上と人手不足の解消
建設就業者数はピークの1997年から大幅に減少し、55歳以上が3割を超える状況となっています。就業者の高齢化と若手入職者の減少が進み、熟練技能者の大量離職も目前に迫っています。限られた人材で社会を支え続けるためには、抜本的な生産性向上が急務です。
デジタルツインは、建設プロセスのあらゆる場面で生産性を高めるポテンシャルを秘めています。
- 遠隔での現場管理:現地に行かなくても、リアルタイムで施工状況を正確に把握
手戻りの削減:設計データと現場の状況を常に比較し、ズレを早期に発見
若手への技術継承:熟練技術者の動きをデータ化し、教育・訓練に活用
国内外で加速するデジタルツインの取り組み

デジタルツインの活用は、一企業の取り組みに留まらず、国や自治体を挙げた国家規模のプロジェクトとして、各国で推進されています。
PLATEAU|日本
「PLATEAU(プラトー)」は、国土交通省と民間企業が連携して推進する、日本全国の都市デジタルツイン実現プロジェクトです。
日本全国の3D都市モデルを整備し、オープンデータとして公開することで、防災計画や都市開発、交通計画など、さまざまな分野での活用を目指しています。災害リスクの可視化や避難シミュレーションなど、安全なまちづくりの基盤となることが期待されています。
【参考】国土交通省「日本全国の都市デジタルツイン実現プロジェクト PLATEAU」
デジタルツイン実現プロジェクト|東京都
「デジタルツイン実現プロジェクト」は、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させ、都民のQOL(生活の質)向上を目指す、東京都が推進するプロジェクトです。
防災・減災からインフラ管理、行政サービスの向上まで、あらゆる分野でデジタルツインを活用し、2030年までの社会実装を目標に掲げています。2025年現在は、分野ごとの段階的な実証が進められています。
【参考】東京都「デジタルツイン実現プロジェクト」
VIRTUAL SHIZUOKA構想|静岡県
静岡県は、県土をレーザースキャナーで測量して、丸ごと仮想空間上で再現する「VIRTUAL SHIZUOKA構想」を2019年度から推進しています。
このプロジェクトの大きな目的は、仮想空間の中に1分の1スケールの静岡県を構築し、デジタルツイン時代における新たな社会インフラとして活用することです。デジタルツインを利用して防災対策や観光対策を効率的に進め、より魅力的な静岡県を目指しています。
【参考】静岡県「静岡県が進める VIRTUAL SHIZUOKA構想 とは?」
バーチャル・シンガポール|シンガポール
バーチャル・シンガポールは、国土全体を3Dモデル化し、建物やインフラのみならず、気候や人口統計といった多様な情報をリンクさせる取り組みです。シンガポールにおけるデジタルガバメント施策「Smart Nation Singapore」の一環として、2014年にスタートしました。
アプリケーションの開発に役⽴てられたり、地下埋設物のデータが作成されたりするなど、世界でも特に先進的な取り組みとして知られ、都市計画のシミュレーションや新たなサービスの開発基盤となっています。
【参考】国土交通省「スマートシティとこれからのデータ プラットフォーム構築の課題」
ヘルシンキ 3Dモデル|ヘルシンキ
デジタルツインに関する取り組みは、フィンランドでも実施されています。ヘルシンキ 3Dモデルは、フィンランドの首都・ヘルシンキを仮想空間の中で忠実に再現し、都市開発や公共サービスの向上に役立てる取り組みです。
このプロジェクトでは、建物はもちろん水部や橋梁、樹木などもできる限り再現されているのが特徴です。また、建物が新築されたり取り壊されたりしたときにも、BIMを利用してデータを更新するなど、先進的な取り組みも実施されています。
【参考】東京都都市整備局「【参考事例】ヘルシンキ 3Dモデル」(p1)
バルセロナ スマートシティ|バルセロナ
スマートシティの先進都市として知られるスペインのバルセロナでは、交通機関の運営や公共施設の管理などにIoT技術を導入するなど、2000年頃からスマートシティの構築に取り組んできました。
現在もデジタル化に向けた方針のもと、オープンソースやオープンイノベーションを前提とした数多くのプロジェクトに取り組んでいます。デジタルツインは、スタジアムの人流解析や仮想空間でのシミュレーションなど、さまざまな場面で活用されています。
【参考】東京都都市整備局「【参考事例】バルセロナ スマートシティ」(p4)
現場はこう変わる!インフラ整備におけるデジタルツイン活用事例

デジタルツインは、実際の建設現場やインフラ管理の現場をどのように変えているのでしょうか。国内の具体的な事例を見ていきましょう。
【事例1:静岡県熱海市】災害復旧での迅速な意思決定を実現
先ほど紹介した「VIRTUAL SHIZUOKA構想」は、2021年7月に熱海市で発生した土石流災害で真価を発揮しました。仮想空間上の静岡県を活用して、災害の状況を把握したり、対策を検討したりといった施策が実行されています。
具体的には、災害発生後、ただちに「静岡点群サポートチーム」を結成し、ドローンなどで迅速に現地の3Dデータを取得。事前に整備していたデータと比較することで、土石流の流下範囲や崩壊箇所などを正確に把握し、迅速な復旧計画の立案と二次災害の防止に大きく貢献しました。
【参考】静岡県「静岡県が進める VIRTUAL SHIZUOKA構想 とは?」
【事例2:松川ダム】ICT施工と連携した最先端の施工管理
長野県の松川ダム掘削工事では、ドローンやレーザースキャナーで取得したデータをもとに、現場の「今」をデジタルツインで再現。総土量約11万㎥におよぶ広大な現場管理の効率化を実現しています。
設計データと現場の差異をリアルタイムで比較・可視化
オフィスにいながら広大な現場の進捗状況を正確に把握
土量の計算や重機の配置計画を最適化
これにより、建設プロセス全体が効率化され、工期短縮や手戻りの削減といった大きな成果につながりました。
デジタルツインが拓く建設業の未来

最後に、デジタルツインが建設業、そして私たちの社会をこれからどのように変えていくのか、その未来像と課題を見ていきましょう。
インフラのライフサイクル全体を最適化
デジタルツインは、インフラのライフサイクル(計画→設計→施工→維持管理)のすべてをつなぎ、最適化する基盤技術となり得ます。以下のような活用が期待されています。
【設計・施工における活用】
・設計段階で、建物の3Dモデルを作成
・デジタルツイン上での詳細なシミュレーション
・設計ミスの早期発見や手戻りの削減
・施工プロセスを仮想空間上で再現
【維持管理における活用】
・ドローンなどから取得したリアルタイムデータを、デジタルツインへ反映
・インフラの状態を常に監視
・劣化の兆候を早期に発見し、効率的な修繕計画を立案
予測を可能にし、災害に強い社会を実現
都市全体のデジタルツインを構築することで、さまざまな災害シミュレーションが可能になります。「VIRTUAL SHIZUOKA構想」のように都市全体のデジタルツインを構築しておけば、ハザードマップが作成できるほか、有事の際の迅速な対応に向けても有効と言えるでしょう。
【防災・減災における活用】
・地震や洪水、土砂災害などのシミュレーションを実施
・災害リスクの高いエリアや避難経路を特定
・より実効性の高い防災計画を策定
【災害復旧における活用】
・被災地の状況を、デジタルツイン上でリアルタイムに把握
・救助活動や復旧作業の優先順位を迅速に判断
空港分野での新たな活用可能性
空港も、災害時の緊急輸送拠点やエネルギー供給拠点としての役割を担う、重要な社会インフラのひとつです。そのため、空港へのデジタルツイン活用も、防災・減災およびインフラ維持管理の観点から注目されています。
国土交通省の資料によれば、空港におけるデジタルツインは以下のような効果をもたらします。
- 混雑予測や導線シミュレーションを行い、より快適な移動・サービス提供を実現
利用状況に応じた設備管理や省エネ運用を可能にし、施設の運営効率を高める
センサーや3Dモデルを組み合わせ、設備の劣化や不具合を早期に検知
空港のように大量の人と設備が複雑に関わる施設では、デジタルツインが「運用・管理の見える化」と「持続可能な運営」の基盤となることが期待されています。
【参考】国土交通省「空港施設設計におけるデジタルトランスフォーメーションへの取り組み ~デジタルツイン技術を活用した展開ビジョンについて~」
普及に向けた課題と今後の展望
デジタルツインの可能性は無限大ですが、その普及にはいくつかの課題も存在します。「リアルタイム更新」はその代表例のひとつと言えるでしょう。
デジタルツインは、リアルタイムでのデータ更新を理想としていますが、実際には災害時のセンサー故障や、工事の内容によっては測量機器を設置できない場合が散見されます。また、通信遅延や処理遅延、ノイズや欠損データへの対応といった課題も見逃せません。
そのほかにも、以下のような課題が挙げられます。
データの標準化:異なるシステム間でのデータ連携をスムーズにするためのルール作り
セキュリティ対策:サイバー攻撃などから社会基盤データを守る強固なセキュリティ
導入コスト:初期投資やランニングコストの確保
人材育成:BIM/CIMの運用経験や、IoT、AIの知見を持つ技術者の育成
データの標準化は、国際的にも議論が進んでおり、ISO 23247(製造業向けデジタルツインフレームワーク)をはじめとする国際標準が整備されつつあります。
また、今後はAI(人工知能)との連携も加速するでしょう。AIがデジタルツイン上の膨大なデータを分析し、最適な施工計画を自動で提案したり、インフラの異常の兆候を自律的に検知したりする未来も遠くありません。
これらの課題を官民一体で解決していくことで、デジタルツインはさらに発展していくでしょう。
【参考】国土交通省「デジタルツインによる冬期道路交通マネジメントシステムの技術開発」
【参考】一般財団法人日本規格協会「海外標準化動向調査(7月)」
デジタルツインは建設業の未来を支える新たな「社会インフラ」へ
デジタルツインは、単なる建設現場の効率化ツールにとどまりません。それは、防災・減災やインフラの維持管理、そして国民の安全・安心な暮らしを守るための、新しい社会基盤そのものです。
デジタルツインの導入には、リアルタイム更新やデータの標準化、人材育成など、まだ乗り越えるべき課題も少なくありません。しかし、官民一体となった取り組みが進む今、この新しい技術はより安全で持続可能な社会を築く原動力となるでしょう。エネルギー効率化やCO₂削減、住民参画型の都市計画といった観点でも、新たな社会インフラとしての役割が期待されています。
建設業の変革を通じて、社会全体のあり方や私たちの暮らしそのものを変えるポテンシャルを持つデジタルツイン。その可能性を現実のものとすることが、次代を担う建設業の大きな役割ではないでしょうか。

監修者 柳川実理(やながわみのり)
一級建築士・宅地建物取引士
2010年に設計事務所へ入社以来、BIMなどの最新デジタル技術を活用し、設計の効率化とクライアントとの意思疎通の円滑化を推進。近年は最新のデジタル技術を活用し、設計から施工をスムーズにつなぐ取り組みを進めている。
DXのコラム
SNSシェア
ニュース
新着情報
- 2026/01/06 『第10回 JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展- トプコン出展ソリューション』を公開しました
- 2025/12/25 『建設リサイクル法とは?契約から完了報告までの流れと現場管理のポイント』を公開しました
- 2025/12/22 年末年始休業のご案内
イベント
- Start Date
- 2026/01/21
- End Date
- 2026/01/21
- Event Name
-
『KANAI SELECTION 2026』
- Event Details
-
日程:2026年1月21日(水)9:00~16:30
会場:新潟市産業振興センター(新潟県新潟市)
主催:金井度量衡株式会社
- URL
- https://www.kanai.co.jp/news/1933/
- Target
- _blank
- Start Date
- 2026/01/20
- End Date
- 2026/02/25
- Event Name
-
TOPCON × KENTEM 共催『面トル体験セミナー』関東トレーニングセンタで開催
- Event Details
-
日程:
2025年11月26日(水)
2025年12月17日(水)
2026年1月20日(火)
2026年2月25日(水)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html
- Target
- _self