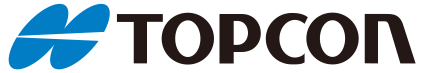- Start Date
- 2026/02/10
- End Date
- 2026/02/10
- Event Details
-
日程:
2025年12月23日(火)
2026年2月10日(火)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、福井コンピュータ株式会社
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-fukui-computer-2h.html
- Target
- _self
DX
i-Construction 2.0とは?現場で実践すべきことや取り組み事例について

建設業界の生産性向上と働き方改革の切り札として、国土交通省が推進する「i-Construction(アイコンストラクション)」。測量から設計、施工、検査に至る全プロセスにICT(情報通信技術)を導入するこの取り組みは、今や「i-Construction 2.0」へと進化し、その動きを加速させています。
しかし、「国土交通省が示す3つの柱とは具体的に何か?」「現場では何をすれば良いのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、i-Construction 2.0が提唱された背景や内容、現場で実践すべきことまで分かりやすく解説します。
i-Construction 2.0とは

国土交通省が提唱する「i-Construction 2.0」とは、建設現場のあらゆるプロセスを抜本的に見直し、生産性を飛躍させるための取り組みです。デジタル技術やAI、ロボットなどを駆使して「建設現場のオートメーション化(自動化)」を推し進め、少ない人数でも安全で質の高いインフラ整備を実現することを目指しています。
この取り組みは、単に工事現場の省人化を図るだけではありません。調査・測量、設計、施工、検査、そして完成後の維持管理まで、建設生産プロセス全体が対象です。
国が掲げる最終的な目標は、2040年度までに建設現場の省人化を3割進め、生産性を1.5倍に向上させることです。同時に、「給与が良い・休暇が取れる・希望がもてる」という新3Kを実現し、建設業界を誰もが働きがいを感じられる魅力的な産業へ変革することも、重要な目的とされています。
【参考】国土交通省「i-Construction 2.0 ~建設現場のオートメーション化~」
なぜ今、i-Construction 2.0が重要なのか
i-Construction 2.0が強力に推進される背景には、日本が直面する3つの大きな課題があります。
生産年齢人口の減少
自然災害の頻発化
インフラの一斉老朽化
日本の急速な高齢化は国の推計にも表れており、高齢化率は2020年の28.6%から、2070年には38.7%に達する見込みです。これに呼応するように、社会の担い手である生産年齢人口(15~64歳)の割合は、同期間に59.5%から52.1%へと減少が見込まれています。
建設業では特に高齢化が進んでいます。2024年の統計によると、就業者の36%以上を55歳以上が占める一方で若手の担い手は不足しており、将来の人材確保が大きな課題となっています。少ない働き手で、頻発する災害への対応やインフラの維持管理といった重大な社会的使命を果たしていくためには、生産性の抜本的な向上は不可欠と言えるでしょう。
【参考】厚生労働省「将来推計人口(令和5年推計)の概要」
【参考】建設業デジタルハンドブック「建設業就業者の高齢化の進行」
i-Constructionの取り組みは2.0へ進化
i-Constructionは、2016年度からスタートしたプロジェクトです。当初の主眼は、3次元データを活用したICT施工の普及でした。これにより、以下をはじめとする成果が挙げられています。
ICT施工:ICT施工を実施できる直轄土木工事の87%で実施(2022年度時点)
作業時間:ICT施工により、2015年度と比較して作業時間を平均約 21%短縮
ICT施工の公告件数:2016年度の84 件から、2022年度には13,429件へと増加
しかし、ICT施工の導入だけでは生産性向上に限界が見え始めたのも事実です。そこで、より踏み込んだi-Construction 2.0が始動しました。
i-Construction 2.0では「ICTの導入」から「現場のオートメーション化」へとフェーズを進め、次に紹介する「新たな3つの柱」を掲げて、建設業界の構造そのものを変革しようとしています。
【参考】国土交通省「「i-Construction 2.0」を策定しました~建設現場のオートメーション化による生産性向上(省人化)~」
【参考】国土交通省「i-Construction 2.0 ~建設現場のオートメーション化~」
i-Construction 2.0が掲げる「3つのオートメーション」

i-Construction 2.0では、建設現場の生産性を飛躍させるために「3つのオートメーション化」を柱として掲げています。
施工のオートメーション化
これまで人が建機を直接操作していた施工を、ICTやAI技術を用いて自動化・遠隔化する取り組みです。例えば、以下のような技術活用が想定されています。
各種センサーによる現場状況の自動計測・記録
異なる建機メーカーが取得した施工データの共有・統合
建設現場のリアルタイムな可視化
AIを活用した最適な施工計画の自動作成
一人のオペレーターによる複数建機の遠隔協調操作
このような技術を活用すれば、わざわざ現地を見に行かなくても、事務所のシステム上で施工状況を確認したり、建設機器の配置を見直したりでき、管理業務の効率化を図れます。
ただし、建設現場の可視化や自動化を実現するには、現場へのICT建機ならびに関連設備の導入はもちろん、遠隔施工を支える技術開発とその普及が欠かせません。
こうした背景から、施工データを一元管理できるシステムの導入が重要と言えるでしょう。このようなシステムの活用により、異なるメーカーの機器が取得したデータでも、関係者間での効率的な共有が実現します。
今後は個社の努力だけでなく、自動施工における標準的な安全ルールの策定や、メーカーの垣根を越えた建機の連携など、業界全体でのルール作りや技術の標準化も求められると言えるでしょう。
データ連携のオートメーション化
調査・測量から維持管理まで、建設の全工程で生まれる膨大な情報をデジタルでつなぎ、一元的に活用する取り組みです。同じデータを二度打ちしたり、不要な問い合わせをしたりする無駄をなくし、プロセス全体の生産性を向上させます。
具体例は以下のとおりです。
BIM/CIMの3次元設計データを、そのまま施工データとして活用
書類や図面をデジタル化し、ペーパーレス化を推進
デジタルツイン(物理空間の情報を仮想空間に再現する技術)で施工をシミュレーションし、手戻りを防止
ただし、建設プロセスにおけるデータ連携は容易ではありません。そのため、BIM/CIMを軸としたデータの一元管理や、3次元モデルの利用を標準化していく必要があります。誰もが必要な情報にすぐアクセスできる、共通の情報共有プラットフォームの整備が今後の課題となるでしょう。
施工管理のオートメーション化
これまで人が現場に赴いて行っていた品質管理や安全管理を、遠隔技術(リモート)や現場外(オフサイト)からの支援によって効率化する取り組みです。例えば、次のような省人化・高度化が進められています。
段階確認などで活用されてきた「遠隔臨場」を、立会検査にも適用
デジタルカメラで撮影した画像をAIが解析し、コンクリート構造物の配筋の出来形(間隔・本数など)を確認
工場であらかじめ製造したプレキャスト製品を、大型構造物にも導入推進し、現場作業を削減
ロボットが人の代わりに危険箇所や広範囲の出来形を検査
従来の現場巡回や対面での検査は、多くの時間と人手を要していました。こうした管理業務の省人化を実現するには、ロボットや画像解析といった新技術の導入はもちろん、動画や3次元モデルといった大容量データを円滑に利用できる、高速通信ネットワークの整備も欠かせません。
i-Construction 2.0のメリットと、現場で実践すべきこと

i-Construction 2.0の推進は、建設現場にどのような変化をもたらすのでしょうか。企業やフィールドワーカー(現場従事者)が得られるメリットと、現場で実践すべき具体的なアプローチを紹介します。
i-Construction 2.0を推進するメリット
建設現場でi-Construction 2.0を推進することで、次のようなメリットが期待できます。
- 生産性向上による工期の短縮
- 省人化によるコスト削減
- データ活用による施工精度の向上
- 手戻り作業の防止による無駄の削減
- 危険作業の代替による労働災害リスクの低減
- 職場環境の改善を通じた人材確保と定着
企業にとってICTやAIの導入は、工期短縮や人件費削減といった直接的な利益向上につながります。それだけでなく、生産性・安全性・快適性の向上は、建設業界のイメージを刷新し、若手人材を惹きつけるための不可欠な要素となるでしょう。
建設現場で実践すべきこと
i-Construction 2.0を自社に浸透させるには、単に機器を導入するだけでは不十分です。「ハード」と「ソフト」の両面からアプローチを行いましょう。
【ハード】ICT建機やシステムの導入
自社の課題や予算に合わせて、ICT建機やドローン、BIM/CIMソフト、情報共有システムなどを計画的に導入します。
【ソフト】人材育成と文化の変革
新しい技術を使いこなせる人材を育成すると同時に、デジタル化への抵抗感をなくす取り組みが重要です。既存のやり方を一方的に否定するのではなく、ベテランが持つ豊富な知見とデジタル技術を融合させる視点が欠かせません。フィールドワーカーの一人ひとりが「楽になった」「安全になった」と感じられる成功体験を積み重ねていくことが、組織全体の文化を変革する原動力となります。
i-Construction 2.0の取り組み事例

※画像はイメージです
国土交通省はi-Construction 2.0の実現に向けて、各地で試行工事を進めています。「「i-Construction 2.0」の 2025 年度の取組予定をまとめました」や「BIM/CIMポータルサイト」などから、その一部をピックアップして紹介します。
成瀬ダム堤体打設工事(秋田県)
ダムの堤体打設という大規模工事において、本格的な自動施工を目指した試行工事です。自動ダンプや自動ブルドーザ、自動振動ローラといった多数の無人建機を連携させ、ダムの盛土作業を行いました。
特筆すべきは、現場から400kmも離れた指令室から、わずか3名のオペレーターが合計14台もの自動建機を遠隔監視した点です。これにより、未来の遠隔施工と大幅な省人化の可能性を実証しました。
【参考】国土交通省「「i-Construction 2.0」の 2025 年度の取組予定をまとめました」
霞ヶ浦導水石岡トンネル新設工事(茨城県)
霞ヶ浦と他の河川を結ぶ導水路を建設するプロジェクトの一環として、シールドトンネル内での掘削土砂の積込み作業に自動バックホウが導入されました。
この試行では、1人の作業管理者が、狭いトンネル内で稼働する複数台の自動バックホウの状態をリアルタイムで管理し、生産性と安全性の両立を実現しました。この成功を受け、実用化に向けた具体的な安全ルールの策定が期待されています。
【参考】国土交通省「「i-Construction 2.0」の 2025 年度の取組予定をまとめました」
荒川第二調節池下大久保下流工区囲繞堤工事
荒川第二調節池における工事では、BIM/CIMを活用したデータ連携により、現場管理や検査業務の効率化を図っています。具体的には、施工履歴データのCIMに出来形管理や品質管理の確認項目といった属性を付与し、帳票などの一元管理と省力化を実現しました。
また、CIMを活用してデータを色分けし、状況を視覚的に把握しやすくしたことも大きなポイントです。これにより、経験の有無に関係なく、現場管理や検査を効率よく実施できるようになりました。
【参考】国土交通省 BIM/CIMポータルサイト「3次元データで監督・検査の効率化」
大河津分水路山地部掘削その21工事(新潟県)
大河津分水路の治水能力を高めるための掘削工事では、デジタルツインを活用して施工管理の合理化・効率化が図られました。デジタルツインとは、物理空間の情報をデジタル空間の中で双子のように再現する技術です。
広大な施工現場では、出来形の測量や進捗状況の把握に膨大な時間と労力がかかってしまいます。この工事においては、出来形管理用のデジタルツインを構築し、施工管理や検査を効率化しました。
【参考】国土交通省 国土技術政策総合研究所「デジタルツインを活用した施工状況の確認・把握の効率化」
塩殿遊水地整備その4工事(新潟県)
塩殿遊水地の整備においては、無人バックホウの遠隔操作により、掘削や法面整形が進められました。この工事の大きな特徴は、現地から離れた遠隔操作室にて、オペレーターが安全かつ効率的に施工を進めた点です。
具体的にはマシンガイダンスを活用することで、設計データと無人バックホウの現在位置のズレをオペレーターが正確に把握し、遠隔操作の精度を高めました。
【参考】国土交通省「「i-Construction 2.0」の 2025 年度の取組予定をまとめました」
i-Construction 2.0が建設業の未来を拓く
i-Construction 2.0は、単なる技術導入のスローガンではありません。日本の建設業界が、未来においてもその社会的使命を果たし続けるための、壮大な戦略と言えるでしょう。
2040年度に「生産性1.5倍」という目標を達成するためにも、ICT施工やBIM/CIMデータの活用は大前提です。しかし、真の変革は、最新システムを導入するだけで生まれるわけではありません。
成功の鍵を握るのは、データを価値に変える「人材」の育成と、変化を恐れない「組織文化」の醸成と言えます。そして、この挑戦は個社の努力だけでは成し遂げられません。国やメーカー、建設会社、そして現場の一人ひとりが同じビジョンを共有し、業界全体で相互に連携しながら、建設業界の未来を拓いていきましょう。

監修者 佐藤拓真(さとうたくま)
1級土木施工管理技士・著者
準大手ゼネコンで土木の現場監督として7年勤務。道路土工、PC上部工、橋梁下部工など受注金額合計200億円以上の工事に携わる。その後、転職を経て、現在は土木工学のブログ「つちとき塾」を運営しながら、建設業関連の仕事に従事する。著書『土木工事が一番わかる(しくみ図解)』
DXのコラム
SNSシェア
ニュース
新着情報
- 2026/01/06 『第10回 JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展- トプコン出展ソリューション』を公開しました
- 2025/12/25 『建設リサイクル法とは?契約から完了報告までの流れと現場管理のポイント』を公開しました
- 2025/12/22 年末年始休業のご案内
イベント
- Start Date
- 2026/01/21
- End Date
- 2026/01/21
- Event Name
-
『KANAI SELECTION 2026』
- Event Details
-
日程:2026年1月21日(水)9:00~16:30
会場:新潟市産業振興センター(新潟県新潟市)
主催:金井度量衡株式会社
- URL
- https://www.kanai.co.jp/news/1933/
- Target
- _blank
- Start Date
- 2026/01/20
- End Date
- 2026/02/25
- Event Name
-
TOPCON × KENTEM 共催『面トル体験セミナー』関東トレーニングセンタで開催
- Event Details
-
日程:
2025年11月26日(水)
2025年12月17日(水)
2026年1月20日(火)
2026年2月25日(水)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html
- Target
- _self