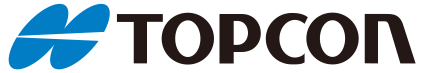- Start Date
- 2026/02/10
- End Date
- 2026/02/10
- Event Details
-
日程:
2025年12月23日(火)
2026年2月10日(火)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、福井コンピュータ株式会社
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-fukui-computer-2h.html
- Target
- _self
時事問題
「レジリエンス(回復力)」とは?土木・建設業に求められる新たな考え方

建設業のフィールドワーカー(現場従事者)にとって重要なレジリエンス。個人や組織が元の状態に回復する力やリスク管理プロセスのことを指します。つまりレジリエンスは「何らかのストレスや困難な状況を乗り越え、回復し、前進する力」と言えるでしょう。例えば、突然のトラブルが発生した際に迅速に問題を把握し、解決策を実行する能力が挙げられます。
この考え方が生まれる以前は、個人に「困難に陥らない状況づくり」「困難な状況にあっても強くあり続ける力」が求められていました。しかし、ストレス負荷が大きい現代において、そのようなあり方は難しくなっています。
建設業で働くにあたって、どのような取り組みがレジリエンス向上につながるか、その内容を理解しましょう。
レジリエンスとは

レジリエンス(resilience)は直訳すると「回復力」を意味する言葉で、「適応力」「順応力」「弾性」と訳されることもあります。レジリエンスは安全管理のためのアプローチのひとつです。ただ一口に安全管理と言っても、大きく分けて3つの側面を有しています。
インフラ回復における社会的な側面
ひとつは、インフラやコミュニティが自然災害やその他の危機に対してどのように耐え、回復するかを示す重要な概念としてのレジリエンスです。
特にインフラのレジリエンスは、災害後の迅速な復旧や機能の回復に関わるものです。例えば、極端な気候変動や地震などの影響を受けた際の道路や橋梁の応急復旧を通じた、早期の通行再開といった取り組みが含まれます。このような対応は、地域住民の安全と生活を守る重要な鍵となります。
東日本大震災後の鉄道復旧がその一例です。JR東日本は、短期間で臨時復旧路線を設置して地域住民の移動手段を確保すると同時に、高架化や津波に耐える構造への改修など、長期的な強化策の導入を実施しました。復旧と同時にレジリエンスを高めるインフラ設計を進め、災害に強い交通網の構築を実現しています。
人的ミスや事故における現場的な側面
人的ミス(ヒューマンエラー)や事故が発生する現場においてのレジリエンスも、ひとつの重要な側面です。単にミスを防ぐだけでなく、ミスが発生した際にどのように迅速に対応し、影響を最小限に抑えるかに関わります。
人的ミスはシステムや環境の不完全さから生じるケースが多く、個人の責任のみに帰することはできません。レジリエンスの観点からは、エラーを単なる失敗ではなく、システム全体を改善する機会と捉えることが重要です。これにより、エラーが発生しにくい環境の構築につながります。
このレジリエンスは、作業手順書をデジタル化し、現場でタブレットを使って確認できるようにするなどの取り組みが挙げられます。作業員の経験に依存しない施工を可能にすることで人的ミスを最小限に留められます。
ストレス回復における精神的な側面
メンタルヘルスの観点からのレジリエンスは、個人がストレスや逆境にどのように対処し、回復するかに焦点が当てられます。
心理学的なレジリエンスは、困難な状況に直面した際に、どれだけ柔軟に対応し、心の健康を維持できるかを示すものです。この力は、メンタルヘルスの維持や、ストレスフルな環境での冷静な判断につながります。具体的には、以下のような要素が含まれます。
- ストレス耐性:ストレスに対する耐性の高さのみならず、ストレスから立ち直る力
- 適応能力: 仕事や日々の生活において、新しい環境や変化に対して柔軟に対応できる力
- 社会的支援の活用:他者との関係を築き、困難な状況下で支援を求め、周囲のサポートを受け入れる力
このようなストレス回復のレジリエンスを高めるためには、マインドフルネスや瞑想を取り入れる、ストレスを感じた時に信頼できる人と話をする、軽いストレッチや運動を習慣にするなど、自分に合った方法を見つけて日常的に取り組むことが大切です。
継続的に取り組むうち、自分のストレスや感情を整理でき、ストレスに対処する力が強化されていくでしょう。
この記事では、主に現場の安全管理や精神的な側面におけるリスク管理アプローチとして、レジリエンスを紹介していきます。
SafetyⅡとレジリエンス

リスク管理のアプローチとしてSafetyⅠ・SafetyⅡが挙げられます。
SafetyⅠは、従来の「リスクを排除する」安全管理方法で、事故やインシデントの原因を分析し、それを防ぐための手段を講じることに焦点を当てた考え方です。
一方で、SafetyⅡは「安全な状態を保ちながら、困難な状況でも対応を続ける」考え方です。現在のレジリエンスでは、SafetyⅠ型の安全管理を行ったうえで明らかになった課題を踏まえ、SafetyⅡの考え方へと変わりつつあります。SafetyⅡのアプローチでは状況に応じた柔軟な対応力が重要視され、SafetyⅠのように計画通りに進むことを前提とはしていないのが特徴です。
| アプローチの手法 | 考え方 | 重視するもの |
|---|---|---|
| SafetyⅠ | 問題が発生しないようにする | 事故やエラーを防ぐこと |
| SafetyⅡ | 変化や異常に柔軟に対応する | システムの安全を維持しながら最適な判断を下す |
土木学会東北支部技術研究発表会の「工事現場におけるレジリエンスSafetyⅡ実施に当たっての一考察」によると、SafetyⅡの考え方は以下のとおりです。
- 対処する(Responding):今直ちに何をすべきか知っている
- 監視する(Monitoring):事態の進行を何に注意を払って監視すべきか知っている
- 予見する(Anticipating):さらにこの先どのような脅威と好機が出現しうるかを知っている
- 学習する(Learning):過去の成功と失敗双方からどんな教訓を引きだすのか知っている
現場や個人のレジリエンスを高めるためには、SafetyⅡの考え方を取り入れることが有効です。
土木・建設業におけるレジリエンスの必要性

レジリエンスを高めること、つまりリスクを把握したりメンタルヘルスを適切にケアしたりすることは、計画通りに進まないケースも多いフィールド(現場)において重要です。建設業にレジリエンスが求められる理由について深掘りしていきましょう。
施工中のトラブル管理とリスク軽減
外的要因による施工中のリスク発生は、土木・建設業において珍しいものではありません。特に資材の輸送や供給の停滞は、外的要因によるリスクの代表例。グローバルなサプライチェーンの影響によって、1つの地域で起きた災害や事故がほかの地域にまで影響を及ぼす事例が増えています。工期や進行に大きな影響を与えるため、迅速な対応力と復旧計画が求められます。
例えば海外からの建設資材供給がストップした際を想定し、国内調達の拡充やリサイクル材の利用、複数の調達ルートの確保など、サプライチェーン全体におけるレジリエンスが重要です。
人的ミスや事故への迅速な対処
土木・建設業では、人的ミスや予期せぬ事故が重大なリスクとなりかねません。現場の安全性を確保しつつ効率的な施工を進めるためには、リスクへ迅速に対応できる体制が不可欠です。また人的ミスを最小限に抑えるための安全教育や、日常的なリスクアセスメントも重要です。
現在ではIoTやセンサー技術を活用したリアルタイム監視が普及し、現場での安全性が飛躍的に向上しています。センサーによって建機やフィールドワーカーの動きがモニタリングされ、危険が察知されると即時に警告が発せられる仕組みを導入する現場も増えています。
また不測の事態が起こった際にフィールドワーカーが迅速に対応できるよう、日々の訓練や危険予知(KY)活動も重要です。関係者へ情報共有できる仕組みが確立されていれば、個々のみならず組織全体としてのレジリエンスが向上し、より安全な現場の実現につながるでしょう。
メンタルヘルスにおけるストレスから立ち直る力の向上
建設業においては、施工中のトラブルやリスク管理が重要であると同時に、従業員のメンタルヘルスを守るためのストレス耐性向上も不可欠です。
レジリエンスではストレス耐性よりも「ストレスから立ち直る力」が重要視されます。いつまでもミスを引きずってしまうと、次のミスを誘発しかねません。レジリエンスを高めることは、現場でのパフォーマンスを向上させ、事故やミスの減少にもつながります。また、従業員が前向きに働けるようになり、離職率の低下も期待できるでしょう。
レジリエンスを高めるための具体的な対策

リスク管理アプローチとしてのレジリエンスを強化するためには、現場での技術革新と労働者の安全管理が鍵となります。土木・建設業では、DXの導入と、SafetyⅡの観点を取り入れた安全管理の向上が求められています。
現場のDX推進
土木・建設業界では、DXの導入がレジリエンス強化の鍵と言えます。DXは現場の効率化のみならず、不確実な状況でのリスク軽減や迅速な回復力の強化にも貢献するものだからです。
例えばドローンの活用はDXの代表的な施策として挙げられるでしょう。ドローンは空からの視点で現場状況をリアルタイムで確認し、被災エリアや危険エリアの詳細なデータ収集を可能とします。特に災害時には、人の立ち入りが難しい危険地帯でも安全かつ迅速に状況を確認できるため、多くの現場で活用されています。
また通常の現場においては、IoTセンサーによってリアルタイムのモニタリングを実施するケースが増えています。フィールドワーカーの位置情報や生体データをIoT技術でモニタリングすることで、熱中症や体調不良のリスクにも対応が可能です。異常が発生した際にはアラートを発信するシステムが導入されているケースもあります。
このようにフィールドワーカーの安全や健康をサポートし、リスクを未然に防ぐためにもDXが活用されています。
フィールドワーカーの安全管理と教育
フィールドワーカーがリスクに適切に対応するためには、最新の安全教育とリスク対応シミュレーションが重要です。現場での不測の事態にも冷静に対応できるよう、災害時や緊急時における避難経路や役割分担、緊急連絡手段について定期的に共有し、シミュレーションを行いましょう。
またSafetyⅡの観点からも、単に事故を予防するだけでなく、事故が発生しそうな場面での柔軟な対応力を養うことが重視されます。個々のスキルを高め、組織全体のレジリエンス向上につなげましょう。
ストレスチェックや各種制度の導入
従業員に対して定期的なストレスチェックの実施を行う会社が増えつつあります。ストレスチェックを行うことで、従業員自身が自分のストレスレベルを把握し、必要な対策を講じられるからです。
これにより早期に問題を発見し、従業員に対して適切なサポートを施すことが可能となります。また、働き方改革を進め、残業や休日出勤を減らし、ワークライフバランスを保つことも重要な取り組みのひとつです。まずは従業員がどのような働き方を望んでいるか、知ることから始めましょう。
レジリエンス向上のための取り組みを理解しよう
何らかのストレスを受けたときに立ち直る力、レジリエンス。土木・建設業においては災害やトラブルへの対応力を高め、現場と従業員の安全を守るために欠かせない考え方です。
現場におけるDXの推進や、ストレスチェックなどの導入といった具体的な取り組みを実践し、変化に対応できる強い現場を築いていきましょう。
時事問題のコラム
SNSシェア
ニュース
新着情報
- 2026/01/06 『第10回 JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展- トプコン出展ソリューション』を公開しました
- 2025/12/25 『建設リサイクル法とは?契約から完了報告までの流れと現場管理のポイント』を公開しました
- 2025/12/22 年末年始休業のご案内
イベント
- Start Date
- 2026/01/21
- End Date
- 2026/01/21
- Event Name
-
『KANAI SELECTION 2026』
- Event Details
-
日程:2026年1月21日(水)9:00~16:30
会場:新潟市産業振興センター(新潟県新潟市)
主催:金井度量衡株式会社
- URL
- https://www.kanai.co.jp/news/1933/
- Target
- _blank
- Start Date
- 2026/01/20
- End Date
- 2026/02/25
- Event Name
-
TOPCON × KENTEM 共催『面トル体験セミナー』関東トレーニングセンタで開催
- Event Details
-
日程:
2025年11月26日(水)
2025年12月17日(水)
2026年1月20日(火)
2026年2月25日(水)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html
- Target
- _self