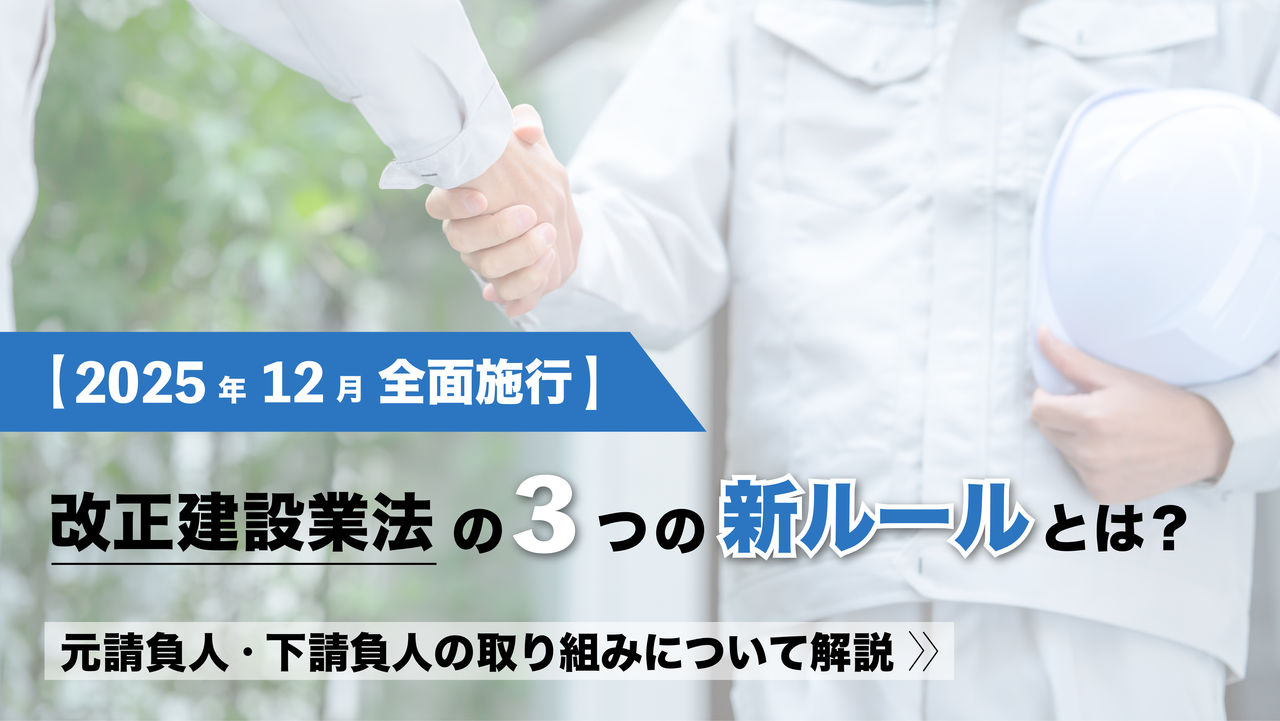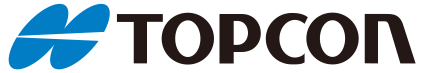- Start Date
- 2026/02/25
- End Date
- 2026/02/25
- Event Name
-
TOPCON × KENTEM 共催『面トル体験セミナー』関東トレーニングセンタで開催
- Event Details
-
日程:
2025年11月26日(水)
2025年12月17日(水)
2026年1月20日(火)
2026年2月25日(水)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html
- Target
- _self
時事問題
バイオディーゼル燃料とは?建設業界で推進される理由と課題

バイオディーゼル燃料は、持続可能な社会の実現に寄与するエコフレンドリーな燃料です。持続可能な社会を目指す流れやカーボンニュートラルの関連政策が推し進められる中、バイオディーゼル燃料はCO₂排出削減と廃油再利用を両立できる「軽油の代替燃料」として、世界的に注目を集めています。
エネルギー政策の方向性や製造コストの高さなどの理由から、欧米に比べて日本では導入が遅れ気味であるものの、今後の建設業界においても重要な選択肢となりうる存在です。
建設業(土木・建築業)でバイオディーゼル燃料の利用が推進されている理由や導入するメリット、使用する際の注意点、既存燃料から移行するにあたっての課題について紹介します。
バイオディーゼル燃料(BDF)とは

バイオディーゼル燃料は、再生可能エネルギーの一種として知られる、軽油の代替となる液体燃料です。菜種油、ひまわり油、大豆油といった植物由来の油脂や、廃食用油などを原料にし、主に「メチルエステル化(※)」という化学反応を用いて製造されます。
英語表記である「Bio Diesel Fuel」の頭文字から「BDF」と称されることもあります。また、バイオディーゼル燃料の中でも、軽油と混合していない100%バイオディーゼル燃料は「B100燃料」と呼ばれます。
※メチルエステル化
油脂とメタノールを反応させ、バイオディーゼル燃料(脂肪酸メチルエステル)を作るプロセス
バイオディーゼル燃料の特徴

バイオディーゼル燃料の最大の特徴として、二酸化炭素(CO₂)の排出量が少なく、環境に優しい点が挙げられるでしょう。
バイオディーゼル燃料も、一般的な燃料と同様に、燃焼時にはCO₂を排出します。しかし、原料となる植物が成長時の光合成によりCO₂を吸収しているため、結果的に、大気中のCO₂量増加は抑えられます。
燃焼時に排出される硫黄酸化物や黒煙といった有害物質が、軽油より少量であることも、バイオディーゼル燃料が注目を集める理由です。また、一部の調整を行えば、通常のディーゼルエンジン車両でそのまま使用でき、汎用性が高いのもメリットのひとつでしょう。
これらの理由から、バイオディーゼル燃料は「次世代の燃料」として注目されています。
建設業界でバイオディーゼル燃料が推進される背景

バイオディーゼル燃料は、建設業における脱炭素化の推進において、重要な役割を果たします。日本政府はGX(グリーントランスフォーメーション)を通じて、持続可能なエネルギーの導入を積極的に推進中です。
国土交通省の「GXの実現に向けた各分野の取組」からも分かるように、国はさまざまな分野においてGXを推進しています。同資料では、建機について以下のように記載されています。
・国内産業部門におけるCO₂排出量の1.4%を占める建設機械について、従前は燃費性能の向上による省CO₂化を進めてきたところであるが、抜本的な機構・システムの見直しが必要。
・そのため、建設現場におけるカーボンニュートラルの実現に向け、動力源を抜本的に見直した革新的な建設機械(電動、水素、バイオマス等)の導入・普及支援策を講じる。
このように、建設業では「材料の脱炭素化」「ICTによる低炭素化」「建機の革新化」が3つの柱とされており、バイオディーゼル燃料は、脱炭素化に向けた有力な選択肢のひとつです。
バイオディーゼル燃料のメリット

バイオディーゼル燃料の使用は、特に環境配慮の側面において大きなメリットがあります。
CO₂排出量が限りなく少ない
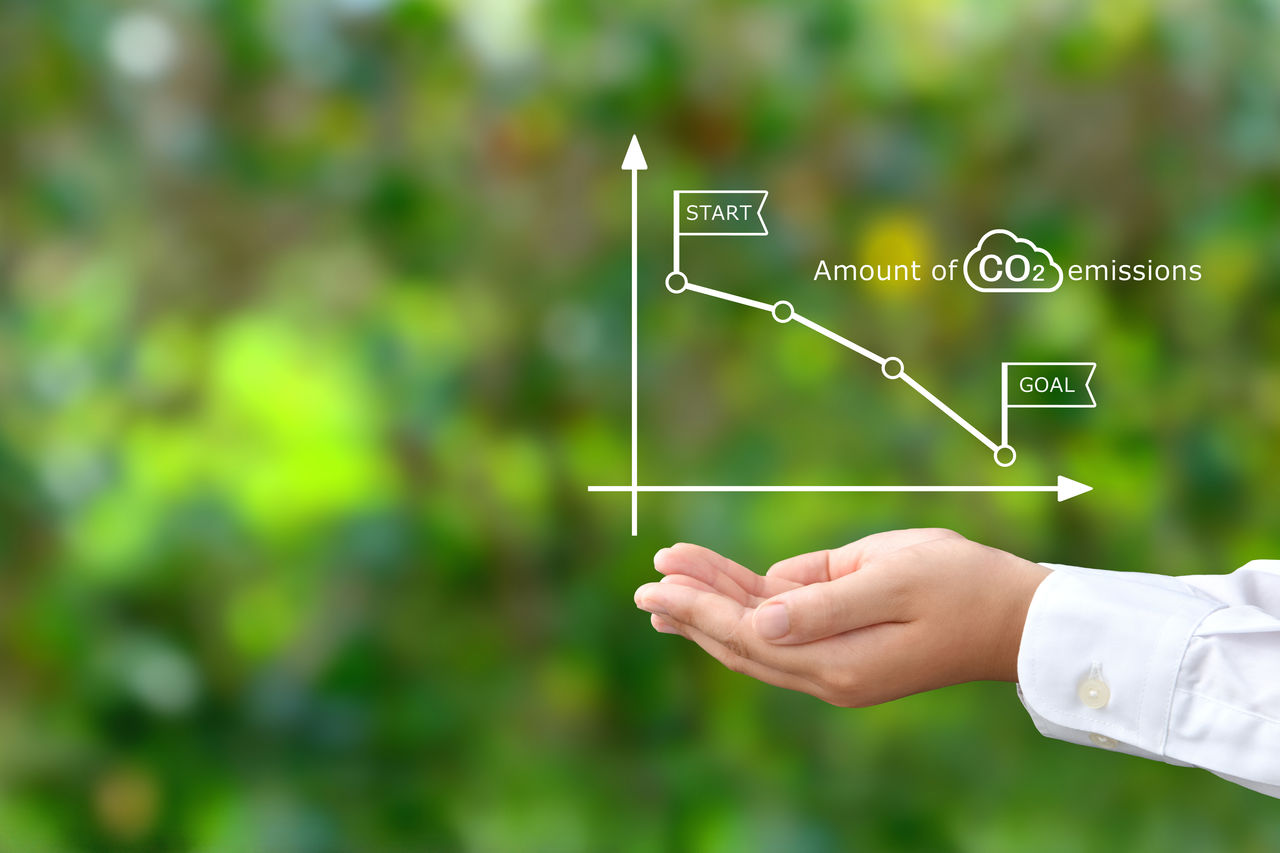
バイオディーゼル燃料は、バイオディーゼル燃料も、一般的な燃料と同様に、燃焼時にはCO₂を排出します。しかし、原料となる植物が成長時の光合成によりCO₂を吸収しているため、結果的に大気中のCO₂排出量が相殺できます。
厳密には、原料の栽培や製造、流通などのプロセスでCO₂は排出されますが、化石燃料の使用と比較してCO₂排出量を大幅に軽減できるため、CO₂排出量の差し引きゼロを実現する「カーボンニュートラル」に近い性質を持っていると考えてよいでしょう。
そのため、バイオディーゼル燃料の使用は、国の「2050年カーボンニュートラルの実現(カーボンニュートラル目標)」や、建設業界の脱炭素化への貢献につながります。
リサイクル効率が高い

廃食用油100リットルからは、約90リットルのバイオディーゼル燃料が精製可能です。そのリサイクル効率の高さから、群馬県高山村(たかやまむら)の廃食用油回収の取り組みをはじめ、バイオディーゼル燃料精製のために動き始める自治体が増えています。
バイオディーゼル燃料に取り組む民間企業や地方自治体などの団体数は、2022年度の調査では108でしたが、2023年度の調査では129へと増加しています。
【参考】全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会「バイオディーゼル燃料取組実態等調査結果(2023年度実績)」
有害物質の排出が少ない

経済産業省の「CO₂等を用いた燃料製造技術開発プロジェクトの研究開発・社会実装の方向性(案)」によると、バイオディーゼル燃料から排出される有害物質「硫黄酸化物(SOx)」は、ほぼゼロです。
バイオディーゼル燃料は、軽油に比べて硫黄分や重金属分の含有量が低く、黒煙の排出を3分の1程度に削減することが可能です。そのため、建機にバイオディーゼル燃料を使用すれば、建設現場の環境改善や従業員の健康リスク低減が期待できます。
既存のディーゼルエンジンで使用可能

バイオディーゼル燃料は、大規模なエンジン改造をすることなく、建機やディーゼル車に利用することができます。燃焼効率や比重が軽油とほぼ同等で、エンジン性能に大きな差はないとされているため、現場での導入ハードルは決して高くありません。
ただし、使用前には法的な申請が必要な場合もあるため、確認は必須です。
軽油引取税が非課税

東京都主税局の「軽油引取税」によると、2025年現在の東京では、軽油などの石油製品と混和せずにバイオディーゼル燃料を使用する場合、地方税法の対象外となり、軽油引取税が課税対象外となります。
同様の取り組みは、埼玉県でも実施されています。また兵庫県では、特定の条件下でバイオディーゼル燃料を混合した軽油のバイオディーゼル相当部分に対して、軽油引取税の課税免除を実施する独自の措置がとられています。
燃料消費量が多い建設業において、これらの措置はコスト面で大きなメリットがあります。
ただし、軽油引取税は都道府県ごとに課される税金であり、適用される規定や手続きは自治体によって異なります。例えば北海道では、バイオディーゼル燃料を軽油などと混ぜて使う場合、事前に知事の承認が必要です。承認を受けずに混和や製造を行うと、罰則が適用される恐れがあります。各自治体へ問い合わせ、事前に確認を行いましょう。
【参考1】埼玉県「バイオディーゼル燃料と軽油引取税制度」
【参考2】兵庫県「軽油引取税」
【参考3】北海道「軽油引取税」
バイオディーゼル燃料を使用する際の注意点

使用するメリットの多いバイオディーゼル燃料ですが、実際に導入する際の注意点も事前に理解し、必要に応じて確認を行いましょう。
定期的な点検とメンテナンスが必要

バイオディーゼル燃料には微量の不純物が含まれることがあるほか、気温が低くなると燃料の流動性が低下しやすい特徴があります。そのため、建機の燃料フィルターが詰まりやすくなってしまいます。水分と結合しやすい特性もあるため、結露によって目詰まりが発生するリスクも無視できません。使用にあたっては、定期的な点検やメンテナンスが必要です。
また、バイオディーゼル燃料を使用すると、建機のメーカー保証が無効となるケースもあります。必ず事前に保証条件を確認しましょう。
なお、(一社)建設業連合会の「建設業における軽油代替燃料 利用ガイドライン」でも、B100燃料使用にあたってのエンジンオイルや消耗品などの点検・交換について、ガイドラインが設けられています。
供給不足と価格の課題

バイオディーゼル燃料は、国内外での供給体制がまだ十分に整っておらず、需要に対して安定的な供給を実現できていないのが現状です。
化石燃料と比べると製造コストの高さが否めないため、価格競争においてバイオディーゼル燃料が不利な状況は大きな課題として挙げられるでしょう。価格が安定しない限り、長期的な使用計画が立てにくい、採算が取れにくいといったリスクは見逃せません。
バイオディーゼル燃料の現状の課題

経済産業省の「資源・燃料政策を巡る状況について」では、原料が限られていることによる供給制約の不安が指摘されています。リサイクル効率は高いものの、原料となる廃食用油や植物油の供給が、需要に追いついていない状況です。
建設業での大規模な持続的利用に対応するためには、原料を多様化させなければなりません。現在、廃油に加わる新たな原料として藻類由来のバイオ燃料の研究が進んでおり、その開発に期待が寄せられています。
【参考】内閣府「藻類による二酸化炭素固定とバイオマス燃料生産」
さらに九州大学の研究「国内バイオディーゼル燃料製造事業 現状打開の糸口を探る!」では、国内におけるバイオディーゼル燃料の⽣産コストは通常の軽油に⽐べて⾼く、価格競争では太⼑打ちできないこと、そして炭素税の導⼊やバイオディーゼル燃料への税⾦の引き下げこそが現状打開の糸口になることが記されています。
バイオディーゼル燃料の導入において、課題は決して少なくありません。しかし、徐々にではあるものの、利用は国内でも広がりつつあります。(一社)建設業連合会の「建設作業所における軽油代替燃料の使用事例集」では、土木・建築工事において、バイオディーゼル燃料が使用された事例が紹介されています。
バイオディーゼル燃料にまつわる課題を解決するには、政府と建設業界が連携し、バイオディーゼル燃料の供給体制の強化や価格競争力の向上を目指す政策の推進が不可欠と言えるでしょう。
バイオディーゼル燃料は建設業界の脱炭素化の糸口となるか
バイオディーゼル燃料は、持続可能な社会を目指す現代において、建設業の脱炭素化を後押しする重要な選択肢です。環境負荷を軽減しつつ、資源を効率的に再利用できるこの燃料が、未来のスタンダードとなる日はそう遠くないかもしれません。
ただし、精製コストの高さをはじめとする導入課題が少なくないのも現状です。技術革新や政策の後押しが進む中、建設業がこの変革にどのように関わるべきか、今一度考えてみてはいかがでしょうか。

監修者 新島 啓司(にいじまけいじ)
技術士(環境部門)
約30年間、環境、再生可能エネルギー、ODAコンサルタント会社に勤務。在職中は自治体の環境施策、環境アセスメント、途上国援助業務の環境分野担当、風力や太陽光発電プロジェクトなど、さまざまな環境に関連する分野のプロジェクトに従事した。
時事問題のコラム
SNSシェア
ニュース
新着情報
- 2026/01/26 『【2025年12月全面施行】改正建設業法の3つの新ルールとは?元請負人・下請負人の取り組みについて解説』を公開しました
- 2026/01/15 『建設会社の社名にはなぜ「組」が付く?由来や歴史について解説』を公開しました
- 2026/01/14 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)対象製品が更新されました
イベント
- Start Date
- 2026/02/10
- End Date
- 2026/02/10
- Event Details
-
日程:
2025年12月23日(火)
2026年2月10日(火)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、福井コンピュータ株式会社
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-fukui-computer-2h.html
- Target
- _self
- Start Date
- 2026/01/21
- End Date
- 2026/01/21
- Event Name
-
『KANAI SELECTION 2026』
- Event Details
-
日程:2026年1月21日(水)9:00~16:30
会場:新潟市産業振興センター(新潟県新潟市)
主催:金井度量衡株式会社
- URL
- https://www.kanai.co.jp/news/1933/
- Target
- _blank