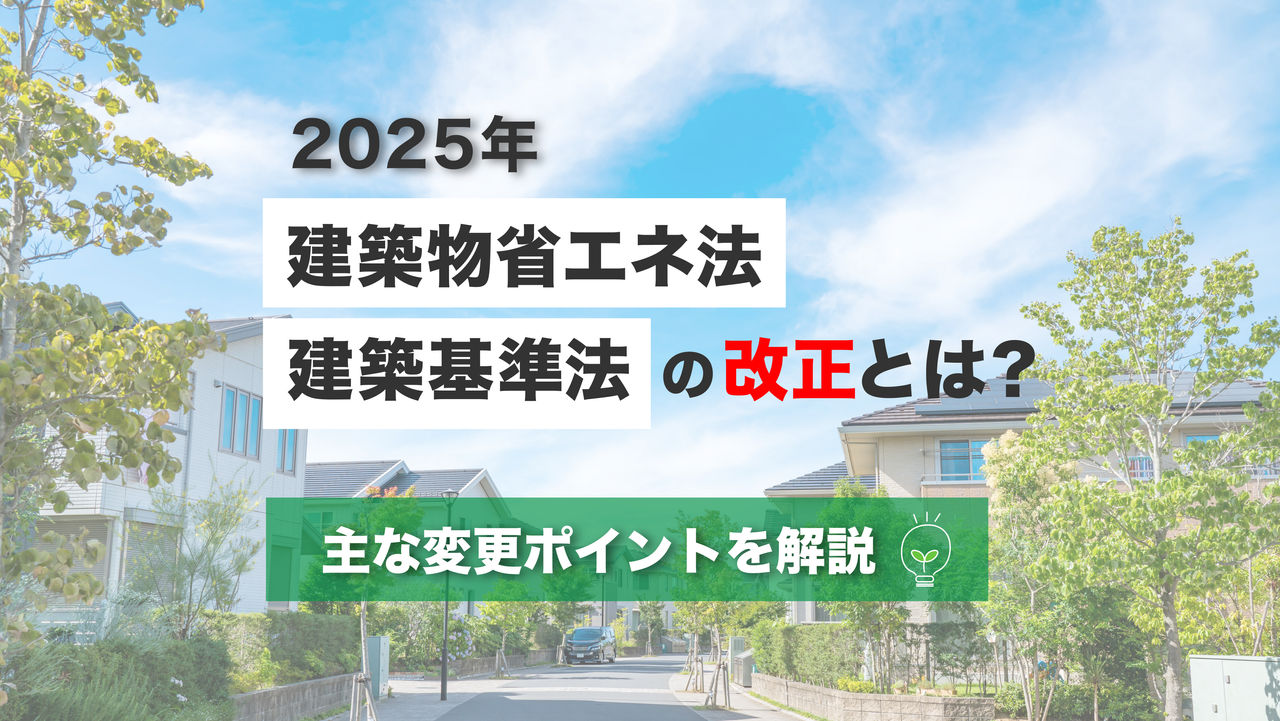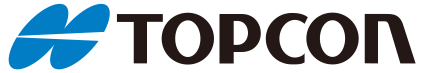- Start Date
- 2026/02/25
- End Date
- 2026/02/25
- Event Name
-
TOPCON × KENTEM 共催『面トル体験セミナー』関東トレーニングセンタで開催
- Event Details
-
日程:
2025年11月26日(水)
2025年12月17日(水)
2026年1月20日(火)
2026年2月25日(水)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html
- Target
- _self
時事問題
建設工事現場の騒音対策とは?作業者と近隣住民の健康を守るためにできること

建設工事現場では、建機の稼働音や電動工具による作業音など、さまざまな音が発生します。まったく音を出さずに工事を進めることはできませんが、過剰に大きな音に対しては、適切な対策を検討することが重要です。対策を行わなければ、フィールドワーク(現場従事者)や近隣住民の健康被害につながる恐れもあるでしょう。
本記事では、フィールドワーカーや近隣住民の健康と安全を守るための騒音対策について、医師監修のもとで解説します。騒音に関連する法律やガイドラインをもとに、実践的な対策やヒントをまとめました。ぜひ騒音対策への理解を深め、働きやすい環境や地域住民との良好な関係性を構築していきましょう。
建設工事現場の騒音リスクとは

建設工事現場では、機器の稼働や大型車両の出入りなどにより、常に大きな音が発生します。騒音が一定のレベルを超えると、フィールドワーカーにも近隣住民にもさまざまな悪影響を与えてしまうため、しっかりと対策しなければなりません。
具体的には、以下のような影響が考えられます。
聴力障害(難聴)
頭痛・めまい・ノイローゼ
睡眠妨害
活動妨害(会話や読書・勉強などの邪魔)
特に注意すべき影響は、騒音による聴力低下です。厚生労働省の「どんな環境で難聴になるの?」では、大きな音を長期間にわたって聞き続けると、有毛細胞がダメージを受け、騒音性難聴を発症する恐れが示唆されています。騒音性難聴には高い音から少しずつ聞こえにくくなるという特徴があり、自分では症状に気づかない場合もあるため注意しましょう。
このような騒音リスクに対応するため、厚生労働省は2023年4月に「騒音障害防止のためのガイドライン」を改訂しました。同ガイドラインでは、騒音レベルの測定、低騒音型機械の導入、聴覚保護具の着用など、大きな音への対策を行うべきことが示されています。フィールドワーカーや近隣住民の健康を守るため、建設工事現場における適切な騒音対策を進めましょう。
騒音レベルとは
建設工事現場における騒音対策を実施するときは、騒音レベルを把握することが重要です。騒音レベルとは、音の大きさを数値化したもので、「デシベル(dB)」という単位で示されます。
従来、騒音レベルは「ホン(phon)」という単位で表されていましたが、1993年の新計量法の施行により、単位はdBに統一されました。ホンは聴感上の大きさを表す単位で、1,000Hz基準のdBと対応しています。
騒音レベルの目安は以下の通りです。
| 騒音レベル(dB) | 日常生活における例 | 建設現場における例 |
|---|---|---|
| 30~40 | 図書館、閑静な住宅街 | ― |
| 50~60 | オフィス、普通の会話 | 事務所内での作業音 |
| 70~80 | 交通量の多い道路、電車内 | 小型コンプレッサー、クレーンの稼働音 |
| 90~100 | 工場内、パチンコ店内 | さく岩機、ブルドーザーの稼働音 |
| 110~120 | 航空機のエンジン付近 | ― |
【参考】暗騒音工法研究会|騒音について
【参考】環境省|生活騒音
騒音レベルが大きくなるほど人間に与える悪影響も大きくなるため、騒音計などを活用して、一定の基準を超えないよう管理しなければなりません。なお、建設工事における騒音については「騒音規制法」によって規制されています。
杭打ち機やブルドーザーを使用する工事など、著しい騒音が発生する建設作業は「特定建設作業」に該当し、騒音レベルや作業時間に制限が設けられています。具体的には下表のような基準があるため、違反しないよう管理を徹底しましょう。
| 規制の種類/区域 | 騒音の大きさ | 作業時間帯 | 作業期間 | 作業日 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号区域 | 敷地境界において85デシベルを超えないこと | 午前7時~午後7時 |
| 日曜日、その他の休日でないこと |
| 第2号区域 | 敷地境界において85デシベルを超えないこと | 午前6時~午後10時 |
| 日曜日、その他の休日でないこと |
第1号区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他
第2号区域:指定区域のうち第1号区域以外の区域
※ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等は、この限りではない
【参考】環境省|住みよい音環境を目指して
建設業に騒音対策が求められる理由

フィールドワーカーや近隣住民の健康を守るため、以下のような法律やガイドラインによって、建設工事現場で騒音対策を実施すべきことが定められています。
| 制定省庁 | 法律・ガイドライン | 目的 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進する | |
| 環境省 | 騒音を規制することで生活環境を保全し、国民の健康を守る |
また、騒音対策を怠ると健康上の問題が発生するだけではなく、以下のような悪影響が出るリスクもあるため注意しましょう。
集中力と生産性の低下
絶え間ない騒音は、フィールドワーカーの集中力低下につながります。作業に集中できずに生産性が低下したり、ミスによる手戻りが発生したりするケースもあるでしょう。ほかのフィールドワーカーと接触する、高所から落下するなど、重大な事故につながる恐れもあります。
環境省の「騒音による各種の影響」によると、騒音レベルが90dB以上の作業環境では、ミスが増えやすいことが示されています。もちろん照明や気温などの影響も受けるため、騒音の影響のみを取り出すことは難しいのですが、騒音によってミスが増加することも考慮し、しっかりと対策することが重要です。
コミュニケーション阻害と安全リスク
建設工事現場で安全かつ効率的に作業を遂行するためには、円滑なコミュニケーションが欠かせません。しかし、騒音が大きくなると、口頭での指示や危険を知らせる声が聞こえにくくなり、伝達ミスや事故が発生するリスクが高まります。
建機との接触事故や落下物による事故など、重大な労働災害につながる恐れもあるため注意しましょう。仮にインターホンやマイク、無線機などの通信手段が整っていたとしても、周囲の騒音レベルが高すぎると円滑なコミュニケーションが阻害されてしまいます。
住民との関係悪化と企業イメージの低下
近隣住民との良好な関係を維持する上でも騒音対策は重要です。特に杭打ち機やブルドーザー、トラクターショベルなどの建機を使用した作業の際は、大きな音が発生します。近隣住民の生活に配慮するため、敷地境界における騒音レベルや作業の時間帯などの基準を遵守しながら工事を進めましょう。
また、近隣住民とのトラブルが大きくなると、企業のイメージや社会的信用の低下にもつながります。工事の円滑な進行を妨げる要因にもなるため、事前にしっかりとした騒音対策を検討しておくことが重要です。
【参考】環境省|住みよい音環境を目指して
フィールドワーカーを守るための騒音対策

ここでは、具体的な騒音対策を3つの観点から紹介します。建設工事現場の安全性と快適性を高めるためにも、適切な対策を講じましょう。
「聴覚保護具」の適切な着用
聴覚保護具の着用は、フィールドワーカーを守るための直接的な騒音対策です。「労働安全衛生規則」第595条や「騒音障害防止のためのガイドライン」によって義務付けられているため、一定の基準を超える騒音が発生する場合は、フィールドワーカーに聴覚保護具を着用させましょう。
代表的な聴覚保護具としては、耳栓やイヤーマフ(耳覆い)が挙げられます。会話が必要な場合は、会話以外の衝撃音だけをシャットアウトする電子イヤーマフが役立ちます。ただし、どのような聴覚保護具でも良いわけではなく、「JIS T8161」規格に基づく十分な遮音性能を持つものを選びましょう。
遮音性能を示す指標にはNRR値・SNR値の2種類がありますが、日本のJIS規格ではSNR値が採用されています。
- NRR値(ノイズ・リダクション・レイティング):主にアメリカ合衆国で採用されている遮音性能の基準
SNR値(シングル・ナンバー・レイティング):日本(JIS)や国際標準(ISO)などで採用されている遮音性能の基準
いずれも数値が大きいほど遮音性が高いことを示す単位であり、「JIS T8161」ではSNR値の基準が採用されています。現場の騒音レベルが100dBで、聴覚保護具のNRR値が30dBの場合、騒音レベルを70dB(= 100dB - 30dB)まで低減させることが可能です。
発生源対策と作業環境の見直し
建機や作業環境など、騒音の発生源を見直すことも重要な取り組みです。
例えば、
- 建機を静音タイプのものに変える
防音カバーを設置する
音が外に漏れないように囲いを作る
といった取り組みは、現場全体の快適さと安全性を高めます。企業としても、事故防止や従業員の健康維持という観点から投資する価値があるでしょう。建機については、国土交通省が公表している「低騒音型建設機械指定状況」から選定することで騒音を抑えられます。
作業環境の見直しとしては、大きな音が出る機器の置き場を工夫するのも有効です。「茨城産業保健総合支援センター 騒音性難聴に関わるQ&A」にも事例があるように、例えば屋内での作業の場合、コンプレッサーをフィールドワーカーが少ない屋外に移動させることで、作業環境を改善できるでしょう。
また、工期に余裕があれば、音の出る作業をほかのフィールドワーカーが少ない日に実施するのも良い方法です。
専門機関への相談
騒音対策として何を行うべきか分からない場合は、専門機関へ相談するのがおすすめです。建設工事現場における騒音対策を検討したいときは、産業保健総合支援センターへ相談すると良いでしょう。産業保健相談員や労働衛生工学専門員が無料相談に応じてくれます。問い合わせ先は、独立行政法人労働者健康安全機構の公式サイトから確認することが可能です。
また、厚生労働省・労働局長登録の株式会社安全教育センターでは、騒音作業従事者のための労働衛生教育を実施しています。費用はかかりますが、専門的な知識を習得したい場合は受講を検討しましょう。
近隣住民を守るための騒音対策

建設工事を進める際は、フィールドワーカーだけでなく、近隣住民への配慮も重要です。騒音公害は住民の生活環境に大きな影響を与え、苦情やトラブル、健康被害に発展する恐れがあります。企業や業界が果たすべき社会的責任として適切な対策を講じ、良好な関係を築いていきましょう。
建設騒音に関する法令の遵守

まずは大前提として、騒音に関する法令を遵守しなければなりません。例えば、騒音規制法や振動規制法に基づく特定建設作業に該当する場合、作業時間帯や作業日数などの基準を守る必要があります。
また、自治体によっては早朝や夜間の工事音には規制が入る場合もあります。あらかじめルールを確認し、法令を守ることがトラブル防止の第一歩です。
環境省は騒音に関する苦情件数などを公表しており、「令和5年度騒音規制法等施行状況調査の結果について」によると、2023年度の騒音に係る苦情の件数は19,890件(前年度20,436件)でした。苦情の内訳は、建設作業が7,466件(全体の37.5%)と、工場・事業場の5,115件を超えて最も多いという結果も出ています。
建設作業が近隣住民に与える影響が大きいことに留意し、近隣住民の生活環境を守るために、法令を遵守して工事を進めましょう。20時以降は子どもの寝かしつけに配慮して大きな音を出さないなど、生活リズムを意識した時間帯設定も重要です。
騒音低減に効果的な取り組みの実施

騒音の拡散を防ぐ、騒音の発生源を見直すなど、騒音低減のためにできる取り組みは少なくありません。ここでは、具体的に実施すべき取り組みを紹介します。
防音シート・防音パネルの設置
建設工事現場の周囲に防音シートや防音パネルを設置することは、騒音の拡散を防ぐ基本的な対策です。国土交通省は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」にて、建設工事における防音対策として、遮音性能の高い防音シートや防音パネルの使用を推奨しています。住宅密集地では、二重構造の防音壁を設置することなども効果的です。
仮囲いの活用
建設工事現場と周辺地域を隔てる仮囲いも、重要な騒音対策のひとつです。公益社団法人 土木学会の「仮囲いによる騒音低減効果の評価」では、仮囲いの設置により、騒音レベルを14~15dB低減できた例が紹介されています。ただし、100Hz以下の低周波音に対しては、騒音低減効果が小さいとの報告もあります。吸音材や鉛シートを併用することで、仮囲いの騒音低減効果が高まる可能性があるため、うまく活用しましょう。
低騒音工法の採用
騒音レベルを大幅に低減できる低騒音工法の採用も有効です。環境省の「建設作業振動に関する手引き」の第5章では、工法や建機の使用について、以下のように記載されています。
鋼矢板、鋼くいを施工する場合は、原則として、油圧式圧入引抜き工法、多滑車式引抜き工法、アースオーガによる掘削併用圧入工法、油圧式超高周波くい打工法、ウォータジェット工法等を採用し、作業時間帯及び低振動・低騒音型建設機械の使用を検討します。
舗装版とりこわし作業では、油圧ブレーカーやハンドブレーカーより、振動の発生が小さいロードカッターや舗装版用圧砕機を使用します。
フィールドワーカーを守るための騒音対策でも挙げたように、国土交通省も建設工事における低騒音工法の採用を促進しています。「低騒音型建設機械指定状況」を参考に建機を選定し、そもそもの騒音の発生源を見直しましょう。
地域住民との良好な関係を築くコミュニケーション

建設工事現場における騒音対策は、技術的な側面だけでなく、地域住民との円滑なコミュニケーションも重要です。公的機関や業界団体も、住民理解と協力の醸成のため、以下のように具体的な事例を提示しています。
事前の説明会と情報提供
工事開始前に、工事概要や騒音が出る可能性のある作業について、周辺住民に向けて説明を行うことも重要です。国土交通省が発行する「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」および「建設工事公衆災害防止対策要綱(土木工事編)」には、工事着手前の近隣住民への周知徹底や説明の重要性が明記されています。
具体的には、以下のような内容を伝えましょう。
事前説明が求められる内容
・工事の概要
・工期
・特に騒音や振動を伴う作業の内容や時間帯
・具体的な対策
・問い合わせ先
苦情への丁寧かつ迅速な対応
事前に説明を行ったとしても、作業状況によっては予想以上に大きな音が発生したり、人によっては不快感を覚えたりすることもあります。
工事開始後に近隣住民からの苦情が寄せられたときは、丁寧に対応しましょう。まずは意見を丁寧にヒアリングすることが大切です。さらに現場の作業状況を確認し、問題がある場合は具体的な改善策を検討しましょう。また、その結果をフィードバックする姿勢も重要です。
地域活動への参加
地域の祭りや清掃活動など、コミュニティが主催するイベントに建設会社として積極的に参加することも有効です。住民との非公式な交流機会を創出することで、信頼関係の構築につながるでしょう。
また、地域活動への参加は、企業の地域貢献活動(CSR活動)の一環としても位置づけられます。工事期間中だけでなく、長期的に良好な関係を築く基盤となるため、各種のイベントには積極的に参加しましょう。
建設工事現場の騒音対策を徹底して健康被害を防ごう
騒音対策を徹底することは、フィールドワーカーや近隣住民の健康を守るだけでなく、「働きやすい環境」と「住みやすい環境」の両立を実現する上で欠かせません。
まずは、作業時間を工夫する・防音シートや仮囲いを設置する・建機や設備のメンテナンス・近隣への事前説明とこまめなコミュニケーションといった、手始めにできる対策から着手してみましょう。
さらに、将来的には静音タイプの建機を導入したり、騒音測定器による数値管理をしたりといった、長い目で見て取り組みたい対策も検討することで、企業イメージの向上と地域社会との良好な関係構築につながるでしょう。
「騒音障害防止のためのガイドライン」なども参考にしながら、自社の現場に合った適切な騒音対策を計画的に実施していきましょう。

監修者 甲斐沼孟(かいぬままさや)
産業医
日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会指導医、日本医師会認定産業医、ほか多数。大阪市立大学(現在の大阪公立大学)医学部医学科卒業。大阪地域の総合基幹病院にて臨床修練経験を積み、現在は大企業産業医として保健衛生活動を積極的に実施している。
時事問題のコラム
SNSシェア
ニュース
新着情報
- 2026/01/15 『建設会社の社名にはなぜ「組」が付く?由来や歴史について解説』を公開しました
- 2026/01/14 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)対象製品が更新されました
- 2026/01/06 『第10回 JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展- トプコン出展ソリューション』を公開しました
イベント
- Start Date
- 2026/02/10
- End Date
- 2026/02/10
- Event Details
-
日程:
2025年12月23日(火)
2026年2月10日(火)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、福井コンピュータ株式会社
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-fukui-computer-2h.html
- Target
- _self
- Start Date
- 2026/01/21
- End Date
- 2026/01/21
- Event Name
-
『KANAI SELECTION 2026』
- Event Details
-
日程:2026年1月21日(水)9:00~16:30
会場:新潟市産業振興センター(新潟県新潟市)
主催:金井度量衡株式会社
- URL
- https://www.kanai.co.jp/news/1933/
- Target
- _blank