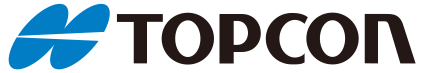- Start Date
- 2026/02/10
- End Date
- 2026/02/10
- Event Details
-
日程:
2025年12月23日(火)
2026年2月10日(火)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、福井コンピュータ株式会社
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-fukui-computer-2h.html
- Target
- _self
働き方
土木・建築の現場に活かせる「主任技術者」「監理技術者」の資格一覧

建設工事の指揮を取る中心的な役割を担う主任技術者や監理技術者は、建設現場への配置が義務付けられています。主任技術者になるには、建設業法で定められた国家資格の取得が必要です。以前は受験にあたって実務経験を必要とする資格が多くありましたが、2024年(令和6年)より施工管理技士資格の受験要件が緩和され、一定年齢以上で誰でも受験できる資格が増えました。
国が定める29種類の建設業から、土木・建築分野で主任技術者として働くための資格を紹介します。資格を取得して仕事の幅が広がればキャリアアップを実現でき、業種によっては年収アップにもつながりやすいでしょう。
自分が働く分野では主任技術者としてどのような資格が求められているのか、まずはその種類を知るところから始めましょう。
主任技術者とは?役割と重要性

建設現場での施工計画策定、品質管理、安全管理、工程管理を担当する主任技術者は、法的要件のもとで工事が計画通りに進むよう、現場をリードする重要な役割を担う存在です。具体的には工事目的や契約条件、現場条件、施工方法、仮設備の配置などの計画を立案し、それに基づいた現場の進行管理などの業務を担当します。
元請や下請、請負金額を問わず、「建設業法第26条第3項」によって、すべての工事現場には主任技術者の配置が義務付けられています。事故防止やトラブル発生時の迅速な対応を可能にする主任技術者は、現場になくてはならない存在です。
基本的には現場専任の主任技術者を配置する必要がありますが、4,000万円未満の土木一式工事または8,000万円未満の建築一式工事においては、複数の現場をかけ持つ非専任の主任技術者の配置でも問題ないとされています。
主任技術者になる方法

建設業には、土木・建築を始めとして、左官、とび・大工、板金、内装仕上など29種類が設けられています。
主任技術者は各現場を管理する司令塔として、現場管理や協力会社の指導といった責任ある役割を担う存在です。主任技術者になる方法は、その種類に応じた資格の取得、実務経験を積む、登録機関者講習の受講という3つのパターンがあります。
資格を取得する
29種別でそれぞれ主任技術者となり得る国家資格は異なるものの、指定の資格を取得することで主任技術者として認められます。
以前は資格の受験要件として学歴に応じた勤務経験が求められていましたが、2024年(令和6年)より、施工管理技士資格の受験要件が緩和。これにより、一定年齢以上で誰でも受験できる資格が増えました。
ただし建設業の種類によっては、資格取得後に一定期間の実務経験が必要だったり、受験の時点で実務経験が必要だったりするケースが存在します。なお2024年現在、土木・建築の種別においては資格取得後の実務経験を要する資格はありません。
実務経験を積む
学歴や国が定めた専攻学科に応じて、一定期間以上の実務経験がある場合も主任技術者になることが可能です。土木工事の場合、土木工学や都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科を卒業すれば、資格を取得しなくても土木工事の主任技術者として活躍できます。
| 卒業区分 | 主任技術者に必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学、短大 | 卒業後3年以上 |
| 高校 | 卒業後5年以上 |
| 上記に当てはまらない者 | 10年以上 |
このように学歴や学科に応じて、最低3年、最長10年の実務経験を積むことで主任技術者として活躍できます。
登録基幹技能者講習を受ける
2018年より、国が指定した登録基幹技能者の講習を受講した人も、主任技術者要件を満たすことが認められました。講習の種類は建設業の種別によって異なり、合計33種類が用意されています。
ただし、土木・建築工事の現場で主任技術者となる場合は、資格の取得または実務経験を積むことが求められます。
主任技術者と監理技術者の違い

主任技術者と似た役割として「監理技術者」が挙げられます。名前は似ていますが、2つの役割と配置基準には明確な違いがあります。
先述したように、主任技術者はすべての建設工事現場に配置が必要です。一方で監理技術者は、より大規模な工事に配置される専門的な管理者であり、主任技術者の代わりとしてその現場全体の責任を持つ役割を果たします。
具体的には、公共工事や大型商業施設など4,500万円以上の下請契約を結ぶ工事または7,000万円以上の建築一式工事においては、監理技術者の配置が必須です。2022年に関連法令の見直しがされ、2023年より以下の要件となりました。
【土木一式工事における要件】
| 見直し前 | 見直し後 | |
|---|---|---|
特定建設業の許可・監理技術者の配置 施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 | 4,000万円 (6,000万円) | 4,500万円 (7,000万円) |
| 主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 | 3,500万円 (7,000万円) | 4,000万円 (8,000万円) |
| 特定専門工事の下請代金額の上限 | 3,500万円 | 4,000万円 |
※()内は建築一式工事の金額
監理技術者が配置される現場において、主任技術者の配置は必要ありません。監理技術者は主任技術者と同様に工事の進捗や安全を管理する技術者です。特に大規模かつ専門性の高いプロジェクト全体の管理を行う立場にあり、下請負人の指導や監督も担当します。
監理技術者になるには、国家資格が必要です。主任技術者同様、必要とされる資格は建設業における29種類の工事によって異なります。例えば建築業であれば、1級建築施工管理技士または1級建築士の国家資格が必要です。
土木分野に関連する主任技術者・監理技術者資格一覧

国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」より、土木分野で主任技術者になれる資格を紹介します。
ダムや道路、橋梁などの大型土木工事から、災害復旧やインフラ整備のプロジェクトで活躍できます。土木領域の主任者資格は、実務経験を必要としないものや、監理技術者として活躍できるものも多いのが特徴です。とはいえ、資格取得の難易度はどれも低くはありません。スキルアップ・キャリアアップを目指し、資格取得に向けて勉強に力を入れましょう。
1級建設機械施工管理技士|対象機械を用いた工事の監督業務を行う資格
ショベルやブルドーザー、ロードローラーといった対象となる建設機械を用いた工事で、指導や監督としての業務に携われる資格です。「建設業法第27条 同施行令第27条の3」によって定められた、国土交通省による国家資格です。
1級合格者には監理技術者の資格が与えられるほか、社会保険労務士の受験資格が付与されます。土木工事以外にも、とび・土工や舗装工事においても監理技術者として活躍できる資格です。学科試験である第一次検定と、実地試験である第二次検定があり、第一次検定に合格すると、施工管理技士補としての資格が得られます。
2023年度(令和5年度)までは、受験資格として学歴に応じた実務経験が必要でした。2024年度(令和6年度)以降は受験要件が緩和され、第一次検定は年度末時点での年齢が19歳以上であれば、誰でも受験できるようになりました。第二次検定の受験資格は以下の要件の通りです。
1級第一次検定合格後、以下のいずれかに該当
・ 実務経験5年以上
・ 特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
・ 監理技術者補佐としての実務経験1年以上
一般社団法人日本建設機械施工協会の発表によると、2024年度の第一次検定の合格率は27.8%、第二次検定の合格率は48.4%となっています。
2級建設機械施工管理技士|対象機械を用いた工事の運転・施工業務を行う資格
1級同様、国土交通省が所管する国家資格です。2級に合格すれば、主任技術者として働くことができます。2級は昭和35年から資格制度が実施され、施工管理技士資格の中では最も長い歴史を持つ資格です。
2級にも第一次検定(学科試験)と第二次検定(実地試験)があります。1級とともに2024年度(令和6年度)以降は受験要件が緩和され、第一次検定は受験年度時点で17歳以上であれば誰でも受験できるようになりました。第二次検定の受験資格は以下の要件の通りです。
2級第一次検定合格後、以下のいずれかに該当
・ 実務経験3年以上(建設機械種目については2年以上)
・ 1級第一次検定合格後、実務経験1年以上
2級では、以下より1種目選択し受験します。1級が対象となる機械を用いた工事で監督業務を行うのに対し、2級は第1種から6種それぞれの機械を用いた工事で、運転や施工の業務に関わります。なお1回の試験で2つの種別を受験可能です。
第1種 ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械による施工
第2種 パワーショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械による施工
第3種 モーター・グレーダーによる施工
第4種 ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械による施工
第5種 アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機等による施工
第6種 くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械による施工
一般社団法人日本建設機械施工協会の発表によると、2024年度の第一次検定の合格率は種別によって25.6~55.2%で、種別計の合格率が41.2%という結果でした。第二次検定の合格率は種別計で51.3%です。
1級土木施工管理技士|土木工事全般の施工管理を行う資格
1級土木施工管理技士は、土木工事の現場において監理技術者として活躍できる資格です。インフラ整備を始めとする大型土木工事や災害復旧工事などで、施工計画の作成や施工管理を行う役目を果たします。工事全体の管理を行う役目として、需要が高い資格といえます。
第一次検定(学科試験)と第二次検定(実地試験)があり、2024年度(令和6年度)から、19歳以上であれば誰でも受験が可能に。土木工事のほか、とび・土工、石、鋼構造物、舗装など8種別で監理技術者として、左官、屋根、タイル・れんが・ブロックなど8種別で主任技術者として働けます。
なお主任技術者となるには、資格取得後、それぞれ当該業種で3年の勤務経験が必要です。国土交通大臣指定試験機関である一般財団法人全国建設研修センターのリリースによると、2024年度の合格率は第一次検定で44.4%、第二次検定で41.2%です。
2級土木施工管理技士(種別:土木)|中小規模の土木工事の施工管理を行う資格
2級土木施工管理技士は、主任技術者として活躍できる資格です。土木・鋼構造物塗装・薬液注入の3つの種別があり、土木工事においては土木の種別が必要です。
ほかの施工管理技術検定同様、2024年度から受験要件が緩和されました。第一次検定(学科試験)、第二次検定(実地試験)と分かれており、第一次試験は受験年度末に17歳以上であれば誰でも受験可能です。
第二次検定は、2級第一次検定合格後に1年以上の実務経験があれば受験できます。国土交通大臣指定試験機関である一般財団法人全国建設研修センターのリリースによると、2024年度の第一次検定合格率は44.6%、第二次検定の合格率は35.3%でした。
技術士|各分野の専門知識を極めて土木工事の監督業務を行う資格
技術士試験に合格し、技術士となることで、監理技術者として活躍できます。技術士制度は、文部科学省による資格認定制度です。科学技術をカバーする国家資格で、建設・機械・金属など21部門に分かれて実施されています。
公益社団法人 日本技術士会の「技術士制度について」では、以下のように定義されています。
「科学技術に関する技術的専門知識と高等の専門的応用能力及び豊富な実務経験を有し、公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた、優れた技術者の育成」を図るための国による資格認定制度(文部科学省所管)
弁護士や弁理士、公認会計士などに並ぶ「5大国家資格」と称されることもある資格です。技術士試験は、第一次試験、第二次試験に分かれて実施されます。
第一次試験の合格で技術士補として、第二次試験の合格で技術士として認められます。第一次試験は誰でも受験が可能で、年齢や学歴などによる制限はありません。第二次試験の受験においては、第一次試験に合格した上で、4年または7年の技術士補経験が求められます。
土木分野で監理技術者となれる技術士資格は以下の5つです。
・建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
・建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
建築分野に関連する主任技術者・監理技術者資格一覧

国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」より、建築分野で主任技術者として活躍できる資格を紹介します。
建築分野において主任技術者や監理技術者となり得る資格は4つのみ。施工管理技士資格は、受験要件の緩和により、実務経験がなくとも第一次検定を受験できるようになりました。建築士資格は、建築系の学歴がない場合は、受験にあたって実務経験が求められます。
1級建築施工管理技士|建築工事全般の施工管理を行う資格
1級建築施工管理技士は、管理技術者として活躍できる資格です。この資格があれば、すべての建築工事の施工計画を作成し、工程や品質、安全面における管理・指導業務を担当できます。
ほかの施工管理技術検定同様、2024年度から受験要件が緩和されました。試験は第一次検定(学科試験)、第二次検定(実地試験)に分かれています。
| 検定区分 | 受験資格 |
|---|---|
| 第一次検定(学科試験) | 受験年度末に19歳以上である |
| 第二次検定 | 所持する資格に応じて1~5年以上の実務経験がある |
例えば第一次検定合格後者は、監理技術者補佐としての実務経験を1年以上積むことで、第二次検定の受験が可能となります。
2級建築施工管理技士(種別:建築)|中小規模の建築工事の施工管理を行う資格
2級建築施工管理技士は、住宅や中小規模の建築工事現場で主任技術者として活躍できる資格です。建築・躯体(くたい)・仕上げの3つの種別があり、建築工事においては建築の種別が必要です。
試験は第一次検定(学科試験)、第二次検定(実地試験)に分かれています。受験要件の緩和により、第一次試験は受験年度末に17歳以上であれば誰でも受験可能となりました。
| 検定区分 | 受験資格 |
|---|---|
| 第一次検定(学科試験) | 受験年度末に17歳以上である |
| 第二次検定 | 所持する資格に応じて1~3年以上の実務経験がある |
一級建築士|建築物全般の設計や施工管理を行う資格
建築分野で監理技術者として働ける資格です。建物の用途や高さ、面積、材質などの制約を受けず、すべての建築物の設計ならびに施工管理ができます。平均合格率は10%前後という難関資格で、学科試験と設計製図試験の2つに分かれて実施されます。
受験要件は厳しく設定されており、必要な学歴や資格を有する以下の人物しか受験できません。
・大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等において指定科目を修めて卒業した者
・二級建築士
・建築設備士
・その他国土交通大臣が特に認める者(外国大学を卒業した者等)
※学歴については、学校の入学年が「平成21年度以降の者」と「平成20年度以前の者」とでは要件が異なる
二級建築士|建築物の設計や施工管理を行う資格
建築分野で主任技術者として働ける資格です。この資格があれば、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など、幅広い材質の建物の設計や施工管理ができます。
直近5年間の合格率は、22~26%程度で推移しています。一級同様、学科試験と設計製図試験の2つに分かれて実施されます。指定科目を修了または建築設備士の資格を所持していれば、実務経験がなくても受験が可能です。
建築に関する学歴がない場合、受験には7年以上の実務経験を必要とします。学歴については、学校の入学年が「平成21年度以降の者」と「平成20年度以前の者」とでは要件が異なります。
現場の種類や規模に応じた資格取得を目指そう
建設業界で働くにあたってぜひ取得したい、主任技術者・監理技術者となるための資格を紹介しました。土木、建築など、携わる現場の種類によって必要な資格は異なり、受験のために必要な要件もさまざまです。
どの資格も取得難易度は低くはありませんが、キャリアアップを狙うなら主任技術者、そして監理技術者へとステップアップしたいところです。現場規模や種類に応じて必要な資格を知り、取得を目指しましょう。
働き方のコラム
SNSシェア
ニュース
新着情報
- 2026/01/06 『第10回 JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展- トプコン出展ソリューション』を公開しました
- 2025/12/25 『建設リサイクル法とは?契約から完了報告までの流れと現場管理のポイント』を公開しました
- 2025/12/22 年末年始休業のご案内
イベント
- Start Date
- 2026/01/21
- End Date
- 2026/01/21
- Event Name
-
『KANAI SELECTION 2026』
- Event Details
-
日程:2026年1月21日(水)9:00~16:30
会場:新潟市産業振興センター(新潟県新潟市)
主催:金井度量衡株式会社
- URL
- https://www.kanai.co.jp/news/1933/
- Target
- _blank
- Start Date
- 2026/01/20
- End Date
- 2026/02/25
- Event Name
-
TOPCON × KENTEM 共催『面トル体験セミナー』関東トレーニングセンタで開催
- Event Details
-
日程:
2025年11月26日(水)
2025年12月17日(水)
2026年1月20日(火)
2026年2月25日(水)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html
- Target
- _self