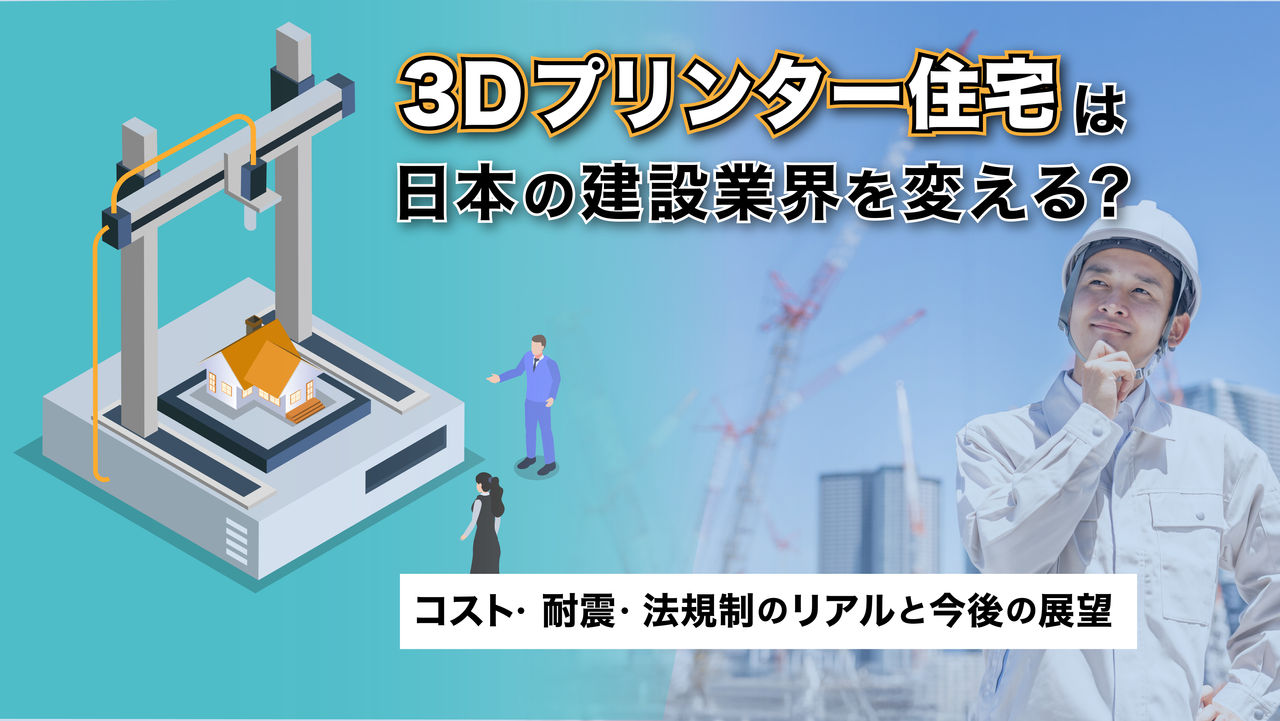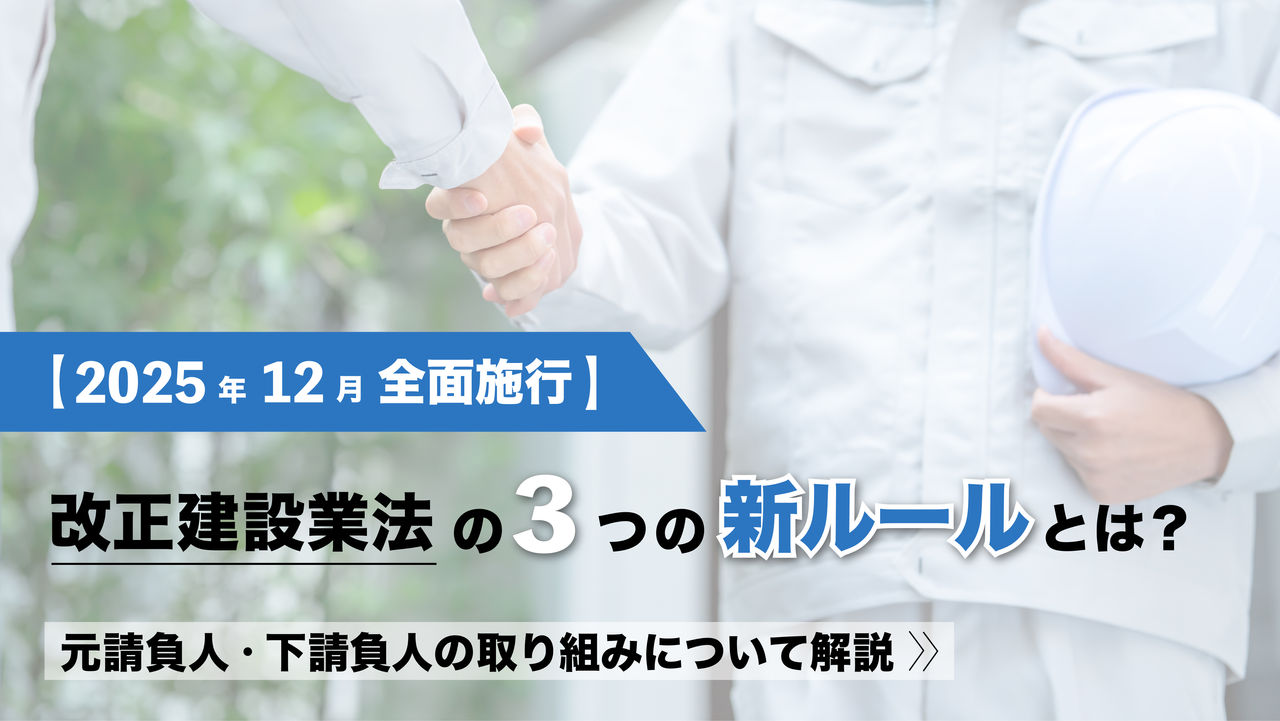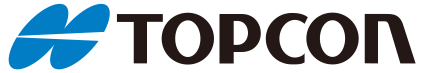- Start Date
- 2026/02/25
- End Date
- 2026/02/25
- Event Name
-
TOPCON × KENTEM 共催『面トル体験セミナー』関東トレーニングセンタで開催
- Event Details
-
日程:
2025年11月26日(水)
2025年12月17日(水)
2026年1月20日(火)
2026年2月25日(水)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html
- Target
- _self
時事問題
労働災害を防ぐ!土木・建設業における安全管理のポイントと事例

危険と隣り合わせの土木・建設業界では慢性的に労働災害が起きやすい状況にあると言われています。墜落や建機による巻き込みといった大きな事故に加え、夏場の熱中症をはじめとする労働災害は、どの現場にとっても深刻な課題です。
2024年4月には、化学物質による労働災害防止を目的に労働安全衛生法が改正されるなど、国も労働災害防止の取り組みに力を入れています。安全管理を徹底し労働災害を防ぐためのポイントや、最新技術を活用した事例を参考に、自社の取り組みに活かしましょう。
労働災害の現状

2024年5月、厚生労働省は2023年(令和5年)分の「労働災害統計」を公表しました。そのデータをもとに、2023年に発生した労働災害の状況を解説します。
2023年(令和5年)の労働災害発生状況
死亡者数が最も多いのは墜落・転落
事故の型別に見ると、すべての業種・建設業ともに死亡者が最も多かったのは「墜落・転落」となっています。
すべての業種
- 墜落・転落 27.0%
- その他 22.1%
- 交通事故(道路) 19.6%
- はさまれ・巻き込まれ 14.3%
- 激突され 6.2%
- 飛来・落下 5.7%
- 崩壊・倒壊 5.0%
建設業
- 墜落・転落 38.6%
- 交通事故(道路) 11.2%
- 飛来・落下 9.4%
- 崩壊・倒壊 8.1%
- 激突され 6.2%
- はさまれ・巻き込まれ 5.8%
- 高温・低温の物との接触/おぼれ 各5.4%
死亡者数が最も多い業種は755人中223人と建設業が1位となってしまったものの、前年に比べると20.6%減少しています。また、建設業が全産業に占める割合も、前年の36.3%から29.5%へと大幅に低下しました。
転倒・転落事故を防ぐためには、安全ネットをはじめとする安全対策が欠かせません。また、身体能力が衰え、負傷が重症化しやすい高齢のフィールドワーカー(現場従事者)には高所作業を免除するなど、現場に即した労働災害防止対策が不可欠と言えるでしょう。
60歳以上の労働災害が全体の約30%
死亡件数が減少傾向にあるのは喜ばしいことですが、かといって決して安心できる状況とは言えません。「労働災害統計確定値」によると、全業種における休業4日以上の死傷者数は135,371人と少なくありません。また、そのうち60歳以上は39,702人と、全体の29.3%を占めています。
とくに60歳以上の労働災害の発生率を30代と比較すると、男性は約2倍、女性は約4倍と飛躍的に上昇。事故の型別にみると、男性の「墜落・転落」における60歳以上の割合は、20代平均の約3.6倍にのぼります。また、年齢が上がるにつれて、休業見込み期間は長くなる傾向にあります。
一般的に、年齢を重ねると身体能力が衰え、転倒のリスクは高まってしまいます。何もないところでもつまずいたり、足がもつれたりして転倒する事故は後を絶ちません。さらに女性は、加齢によって骨折のリスクが著しく高まります。女性の「転倒による骨折等」は、60歳以上は20代平均の約15.1倍と、大きな差が生じています。
労働災害防止に向けた国の取り組み

労働災害防止に向け、国も取り組みを強化しています。2024年には、労働安全衛生法の改正や「第14次労働災害防止計画」の策定といった大きな動きが見られました。
<2024年4月1日>労働安全衛生法の改正
化学物質による労働災害防止のため、2024年4月に労働安全衛生法が改正されました。これにより、リスクアセスメントが義務付けられた化学物質の製造・取り扱い・譲渡提供を行う事業場ごとに「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。また、労働者に保護具を使用させる場合は「保護具着用管理責任者」の専任義務が発生します。
【参考】厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」
<2023年4月~>第14次労働災害防止計画がスタート
厚生労働省による第14次労働災害防止計画は、労働災害を減少させるために国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた中期計画です。化学物質の管理や、60歳以上の高齢労働者に多い転倒や腰痛の予防といった労働災害防止対策を盛り込んでいます。
計画期間は2023年4月から 2028年3月までの5年間で、今計画が目指す社会像は価値観の多様化に対応するものでなければならないと記載されています。計画書にはウェアラブル端末やVR、AIの活用などの内容が盛り込まれ、労働災害防止においてもDXが欠かせないものとされているのが分かります。
【参考】厚生労働省「第14次労働災害防止計画の概要」
建設業における労働災害対策のポイント

建設業界では、現場における安全管理が最も重要な課題の1つです。労働者の命や安全を守るのはもちろん、現場の円滑な業務遂行、また企業の信頼性向上のためにも、安全対策が必要です。適切な安全対策を行えば、危険が伴う作業のリスクを大幅に軽減できます。
安全衛生管理計画の作成
労働災害防止にあたっては、基本方針や目標を定めることが大切です。まず現場のリスクを洗い出し、危険要因を特定します。その次に適切な対策を計画し、作業手順書や安全計画を作成しましょう。
安全教育とトレーニング
安全教育の目的は、労働者の安全を保障し、労働災害の発生を防止することです。企業は従業員に対して適切な安全教育を行う義務があります。適切な設備手順の使用方法、緊急時の対処方法などについての教育を定期的に行い、危険箇所やその対策についての共有も必要です。
新入社員や未経験者には特に注意して教育を行い、OJT(現場教育)を徹底します。適切な安全教育をすることで、従業員一人ひとりの安全意識向上を目指しましょう。
適切な保護具の使用
土木・建設業における労働災害では、ヘルメットを着用せずに作業をしていて頭部を負傷した事例もあります。ヘルメット、安全靴、手袋、ゴーグルなど、作業内容に応じた保護具を支給して使用を義務付けると同時に、保護具が正しく装着されているかを現場で確認することが必要です。
現場環境の整備
作業通路の確保や足場の設置を安全基準に基づいて行います。適切な照明や標識を設置し、視認性を高めることも大切です。
危険な作業の安全対策
作業中に起こりうる事故を想定し、危険予知訓練を行いましょう。雨天時の滑りやすい環境への対処、強風時の飛散物対策も重要です。
また、先述したように、労働災害で死亡者が最も多いのは墜落・転落です。落下防止用ネットの設置、転倒リスクが高い高齢の従業員は高所作業を免除する、あるいは高所作業や建機の運転といった危険な作業には監視者を配置して二重チェック体制を整えるなどの取り組みが有効と言えるでしょう。
定期的な点検と改善
設備や工具の点検を定期的に実施し、不具合があればすぐに改善しましょう。定期点検は、故障や誤作動による事故の予防につながります。それでも、万が一労働災害が発生した場合には、原因を徹底的に調査し、再発防止策を講じることが大切です。
ヒヤリ・ハットの共有
「足場上を走行中、足場板のツメが破損して板が傾き、転落しそうになった」
「ワイヤーが切れ、鋼材が落下した」
これらはヒヤリ・ハットと呼ばれ、幸い重大な事故には至らなかったものの、そうなる可能性があった事例です。1件の重大事故の背景には29件の軽微な事故があり、さらに300件のヒヤリ・ハットがあるとされています。
労働災害を減少するには、ヒヤリ・ハットの段階で確実に危険の芽を摘むことが大切です。国土交通省では、鉄筋工事業、型枠工事業など職種ごとに企業から集めたヒヤリ・ハット体験事例をもとにデータベースを構築し、共有しています。自社のヒヤリ・ハット事例とともに、安全管理の参考にしましょう。社内でヒヤリ・ハットの事例を吸い上げ、共有できる体制づくりをすれば、安全対策に活かせます。
【参考】国土交通省「建設現場の事故防止等のためのヒヤリ・ハット事例等の共有について」
【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト ヒヤリ・ハット事例一覧」
コミュニケーションの強化
厚生労働省の「労働災害原因要素の分析」によると、労働災害の原因の8割はヒューマンエラーとされています。工事の進捗によって作業環境が日々変化し、作業員の顔ぶれも変わる現場では、作業員同士の世代が離れていたり、持ち場が違ったりするとコミュニケーション不足に陥りがちです。
毎朝の挨拶や朝礼などはもとより、作業時にも声かけを積極的に行うことは労働災害を防ぐために大切な取り組みです。ちょっとしたコミュニケーションがあるだけで現場の人間関係はスムーズになり、作業も進めやすくなるでしょう。
また、管理者から作業員への指示がうまく伝わらずに、労働災害につながってしまうケースも往々にしてあります。言った、言わないのトラブルを発生させないためにも、一方的なコミュニケーションにならないよう、きちんと相手に伝わるよう具体的な説明を心がけましょう。
メンタルヘルスケア
作業員のストレスや疲労を軽減して心身の健康を守るメンタルヘルス対策も、労働災害防止の大切な取り組みです。
現在の労働安全衛生法には、メンタルヘルス対策の義務が盛り込まれました。 体の健康をチェックする定期健康診断に加えて、社員の「心の健康」を守っていくことも企業の義務です。
従業員が50人以上の企業は、毎年1回ストレスチェックを実施し、その結果を労働基準監督署に報告することが義務付けられています。従業員のストレス状態を可視化することで、本人もストレスを自覚するきっかけになり、また企業が抱える課題も見えやすくなるでしょう。
最新技術を活用した労働災害防止の事例

労働災害を防ぐには各現場における日々の地道な努力が必要です。ただしその進め方は刻々と変化しつつあります。安全衛生管理の領域にもAIやloTといった最新技術を導入し、効率化を進める企業が増えています。
アナログ作業が多い土木・建設業界はデジタル化が難しいとされてきましたが、従業員の高齢化や慢性的な人員不足、また60歳以上の労働災害が上昇傾向にあることからも、これらの課題解決は急務です。最新のデジタル技術を活用した事例を参考に、自社の安全管理に活かしましょう。
ウェアラブル端末による健康管理・熱中症対策
スマートウォッチやスマートグラスなどに代表されるウェアラブル端末。最近では従業員の健康状態管理や熱中症予防を目的としたスマートヘルメットやウェアラブルセンサー機能付きのウェアが登場しています。
ウェアラブル端末を使用するメリットは、自覚していない健康状態や熱中症のリスクを、端末が判定できる点にあります。搭載されたセンサーが酸素濃度、脈拍、周囲の温湿度情報、心拍数、体温などのデータを総合して健康リスクを判定することで、現場の管理者は従業員の安全を一元管理できます。
また、言語の壁によって健康状態の確認が難しい外国人従業員の健康状態を可視化できるのも大きなメリットと言えるでしょう。個々の健康状態に合わせ、適切な人員配置が可能になり、作業効率のアップにつながります。
ドローンによる測量や安全確認
転落の危険がある高所、足場の悪い場所などでの測量や点検作業には、どうしても危険がつきものです。そこにドローンを導入すれば、従業員の安全を確保できるでしょう。
また、測量は範囲が広く高低差が大きいほど時間も労力もかかりますが、ドローンを使って上空から撮影すれば、現場を歩き回る必要もありません。
災害現場や危険区域、高所といった立ち入りにくい場所の測量にも本領を発揮します。橋梁やトンネルなど老朽化した大規模なインフラ設備の点検にもドローンを活用すれば、従業員を危険にさらす必要がなくなります。
VRを活用したトレーニング
VRが活躍するシーンは安全研修や技術研修です。例えば、VRゴーグルを着用し、現実さながらの仮想空間で作業を行うトレーニングが挙げられます。
実際の建機を使わないため現場経験が少ない従業員でも安全に実施でき、かつ現実に近い空間で作業を体験することで高い学習効果が期待できるでしょう。VRを通じたリアルな体験を通じて、実践的な安全行動を身に付けられます。
AIによるリスク予測
昨今ChatGPTといった生成AIなどで話題のAIも、安全管理の取り組みに有効です。AI技術を応用することで、これらのリスクを予測できます。
<活用事例>
- 建機にAIカメラを設置して、周囲に人がいると察知してアラートをかける
- 過去に起きた労働災害やヒヤリ・ハット箇所などのデータをもとに、事故の発生リスクが高い時期や条件を予測し、具体的なリスク管理策を提示する
- ChatGPTを活用した危険予知システム
- 建設現場の画像を解析し、人が見逃してしまうような小さな危険要因も事前に察知する
建設現場では多くの要素が絡み合った複雑な状況が常に変化するため、リスクを人の目だけで監視するのには限界があります。AIをリスク予測に活用することで、効率的な安全管理が可能です。
デジタル技術を活用して土木・建設業の労働災害防止を
危険な作業が伴う土木・建設業においては、労働災害対策は永遠の命題です。猛暑による熱中症のリスク、従業員の高齢化といった新たな問題もあり、企業はさらに高い水準の安全衛生管理が求められています。最新のデジタル技術を活用すれば、危険な場所での作業をドローンに任せたり、VRを活用して技術指導ができたりと、従業員の安全確保を効率的に実現できます。
DXは安全衛生管理の分野においてもその力を存分に発揮してくれます。紹介した事例を参考に、自社のデジタル変革を加速させましょう。

監修者 松本幸一(まつもとこういち)
社会保険労務士
ハローワーク正職員時代に社会保険労務士試験に合格。その後、社会保険労務士事務所、プライム上場企業人事部勤務を経て、現在は開業社会保険労務士として建設業を含め幅広い業種の顧問先の労務管理に携わる。
時事問題のコラム
SNSシェア
ニュース
新着情報
- 2026/02/16 『3Dプリンター住宅は日本の建設業界を変える?コスト・耐震・法規制のリアルと今後の展望』を公開しました
- 2026/02/16 優遇税制・補助金制度に『中小企業省力化投資補助金(一般型)』が追加されました
- 2026/02/05 『【症状別】建設現場の屋外作業に!市販の花粉症対策グッズ10選』を公開しました
イベント
- Start Date
- 2026/02/10
- End Date
- 2026/02/10
- Event Details
-
日程:
2025年12月23日(火)
2026年2月10日(火)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、福井コンピュータ株式会社
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-fukui-computer-2h.html
- Target
- _self
- Start Date
- 2026/02/09
- End Date
- 2026/03/19
- Event Name
-
建築・設備業者様向け『新製品出前体験会』
- Event Details
-
期間:2026年2月9日(月)~ 3月19日(木)
場所:貴社事務所・現場など
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン
- URL
- https://bc.topconpositioning.asia/bc-demaetaikenkai?utm_campaign=249760459-bc-demaetaikenkai&utm_source=jp-ja&utm_medium=cf
- Target
- _blank